理想の「受発注システム」が
たった1日で見つかる
導入は初めてですか?




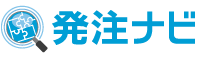
理想の「受発注システム」が
たった1日で見つかる





「注文書のFAXが読みにくく、入力ミスで誤発注してしまった」「電話での受注対応に追われ、他の業務が進まない」「ベテラン担当者の退職で、主要な取引先とのやり取りが滞ってしまった」──。こうした受発注業務における課題は、多くの企業にとって他人事ではありません。 アナログな作業に依存した従来の業務フローは、ヒューマンエラーを誘発し、機会損失や顧客満足度の低下に直結する、深刻な経営リスクです。
本記事では、このような状況を抜本的に改善するソリューションである受発注システムについて、その基本から導入のメリット、そして自社に合った製品の選び方、受発注システムのおすすめ製品(全44製品)までを、受注側・発注側双方の視点から詳しく解説します。システム化によって、煩雑な手作業から解放され、ビジネスの成長を加速させるための一歩を踏み出しましょう。
機能で比較「受発注システム」おすすめ製品一覧
FAXや電話、メールでの受発注業務は、単なる「手間がかかる」だけの問題ではありません。それは、気づかぬうちに企業の競争力を蝕む、重大な経営リスクです。まずは、従来型のアナログな管理を続けることで引き起こされる、4つの具体的な失敗シナリオを紹介します。
読みづらい手書きのFAXや、電話での聞き間違いによる誤発注は、誤った製品の出荷や、不要な在庫の発生に直結します。返品や再発送にかかるコストだけでなく、取引先からの信頼を失うという、金額以上の大きな損失につながる可能性があります。
「この取引先への発注は、ベテランのAさんしか分からない」といった業務の属人化は、非常に危険です。その担当者が急に休んだり、退職してしまったりした場合、業務が完全に停止してしまうリスクがあります。ノウハウや取引履歴が個人に依存している状態は、企業として安定した事業継続の妨げとなります。
電話が繋がらない、メールの返信が遅いといった状況は、発注側にとって大きなストレスです。その結果「もっとスムーズに注文できる仕入先に切り替えよう」と判断され、知らず知らずのうちに売上の機会を失っているかもしれません。また、アナログな処理による納期の遅れや対応漏れは、顧客満足度の低下を招きます。
FAXや一般的なメールでのやり取りは、データとして蓄積・活用することが困難です。「どの製品が、いつ、どれくらい売れているのか」といった販売履歴を即座に分析できないため、在庫の予測やマーケティング施策に活かすことができません。結果として、非効率な在庫管理や、勘に頼った経営判断を続けることになります。
受発注システムは、受注から発注、在庫管理、出荷、請求までの業務をオンライン上で一括管理し、業務効率化と精度向上を支援するIT基盤です。ここでは、まず主要な機能を整理し、次にシステムタイプの分類を解説します。
| 機能名 | 概要 |
|---|---|
| 受注管理機能 | 受注情報をリアルタイムで一元管理。複数チャネルから受注を自動取り込み、納品書や受注伝票の発行が可能です。 |
| 発注管理機能 | 定量発注や発注書の生成・送付が可能。再注文タイミング設定による自動発注も支援します。 |
| 在庫管理機能 | 在庫残数を即時更新し、発注フォームやダッシュボードに反映。欠品・過剰在庫リスクを低減します。 |
| 出荷管理機能 | 出荷スケジュール作成、出荷指示書の発行、配送追跡などによる出荷状況の可視化が可能です。 |
| 請求管理機能 | 受領書や納品書から請求書を自動生成、支払ステータスの管理ができ、ミスのない請求を支援します。 |
| メール自動発信機能 | 受注・出荷・請求の各タイミングで取引先へHTML/テキストメールを自動送信できます。 |
| 発注者ログイン機能(発注者向け) | 取引先が自社管理画面にアクセスして、過去の発注履歴や納期情報を確認可能です。 |
| 他システムとの連携機能 | 販売管理・生産管理・会計システムなどとAPI/CSVで連携し、入力工数を削減します。 |
受発注システムは、自社の業態や規模に応じて「どのようなタイプ」を選ぶかが重要です。利用目的やシステム構成で分類される主な4タイプを以下に紹介します。
あらゆる業種・販売チャネルに対応できる基本機能を備えたタイプです。受注管理・発注管理・在庫管理・出荷処理などの標準機能が揃い、中小企業の業務を幅広く支援します。スモールスタートで導入しやすく、初期段階に適しています。
建設・医療・食品業など、特定の業界特有の処理(例えば、ロット管理、賞味期限管理、現場別請求)に対応できる機能が組み込まれています。汎用型では対応が難しい商慣習や業務フローに適合し、導入後のカスタマイズ工数を削減できます。
ベンダー提供のクラウド上で動作するサービス型です。サーバー構築不要・初期費用低廉で、アップデートや保守もベンダー任せ。サブスクリプション課金により、スケーラブルな利用が可能で、特に多拠点企業やリモート環境に適しています。
自社サーバにインストールするタイプで、カスタマイズ性やセキュリティ制御に優れます。特に情報統制が重要な大企業や、独自運用が前提の企業に向いています。ただし初期導入・運用コストや保守負担が高くなる点には注意が必要です。
おすすめクラウドシステムの基礎知識|クラウド製品・サービスの種類と利点をおさらい受発注システムは、注文を受ける側と出す側の双方に、大きなメリットをもたらします。それぞれの立場で、どのような課題が解決されるのかを見ていきましょう。
BtoBの企業間取引を電子化する仕組みとして、「EDI(電子データ交換)」も一般的です。受発注システムとEDIは似ていますが、それぞれに特徴があります。
| 比較項目 | 受発注システム(Web-EDIも含む) | 従来のEDI |
|---|---|---|
| 導入コスト | 比較的安価(クラウド型なら初期費用無料のプランも) | 高価(専用回線やソフトウェアが必要) |
| 導入期間 | 短期間(数日~数週間) | 長期間(数カ月~) |
| 取引先の拡大 | インターネット環境があれば、新規取引先も簡単に追加可能 | 決まった取引先との接続が基本で、拡大は手間とコストがかかる |
| 画面・操作性 | Webブラウザベースで直感的に操作可能 | 専用のフォーマットが多く、操作には知識が必要な場合も |
【どちらを選ぶべきか】
近年では、受発注システムでありながらEDIの機能も取り込んだハイブリッドなサービスも増えており、両者の垣根は低くなりつつあります。
受発注システムは、企業の受注・発注業務のDXを推進し、効率化と精度向上に寄与します。以下に「導入メリットが高い企業の傾向」と、「製品選びで外せない要点」を整理しました。
次のような課題を抱えている中小・中堅企業では、受発注システムを導入することで業務の標準化と効率化が望め、市場競争力の向上につながることが期待できます。
関連記事【無料版】もあります|受発注システムの選択肢と注意点
自社の課題を解決し、導入を成功させるためには、以下の5つのステップで検討を進めることが効果的です。
まず、自社が製造業、卸売業、小売業、飲食業など、どの業種に属し、どのような商習慣があるかを明確にします。食品業界であればロット管理や賞味期限管理、アパレル業界であればカラー・サイズ別の在庫管理など、業界特化の機能が必要かを検討します。
次に、「必須の機能(Must)」と「あれば便利な機能(Want)」をリストアップします。「在庫管理との連携は必須」「基幹システムとのAPI連携も希望」など、要件を具体化することで、製品の絞り込みが容易になります。
現場の担当者や取引先が、教育に時間をかけなくても直感的に操作できるかは非常に重要です。PCだけでなく、スマートフォンやタブレットからの発注・承認がスムーズに行えるか、無料トライアルなどを活用して必ずチェックしましょう。
企業間取引のデータを扱うため、セキュリティ対策は最重要項目の一つです。通信の暗号化やアクセス権限の管理機能などを確認します。また、導入時やトラブル発生時に、迅速なサポートを受けられる体制が充実しているベンダーを選ぶと安心です。
おすすめSaaS導入前に考慮しておくべき3つのポイント
(製品名 abcあいうえお順)
受発注システムの導入は、FAXや電話といったアナログな業務から脱却し、受注から請求までのプロセスを抜本的に改善するための効果的な手法です。手作業によるミスや手間を削減し、担当者の負担を軽減するだけでなく、データを活用した顧客満足度の向上や、売上増加にも寄与します。
本記事で解説した選び方や導入事例を参考に自社の課題や目的に合ったシステムを選定し、ビジネスのDXを推進させましょう。
「自社に合うIT製品・サービスが分からない」「時間をかけずに効率的にサービスを検討したい」というご担当者様は、ぜひ発注ナビの専門スタッフまでお問い合わせください。適切なIT製品・サービス選定を最後までサポートいたします。