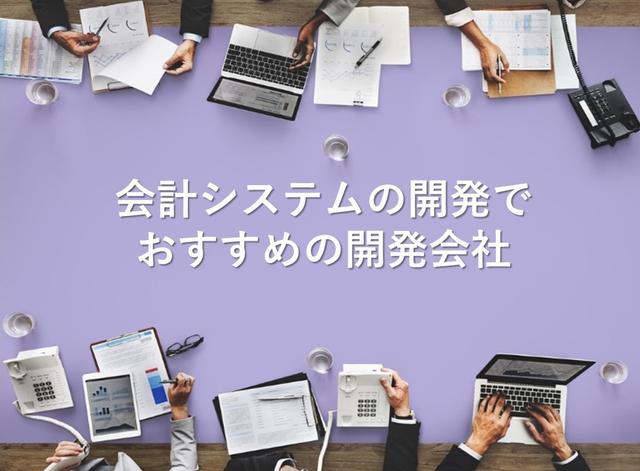年末調整は、所得税を正しく計算して納めるために毎年実施される重要な業務です。しかし、多くの企業が紙書類の管理やミスの発生といった課題に悩まされています。また、申告書の配布や回収、税額計算の手間、提出状況の確認など、どうしても時間や手間がかかるのもネックです。
こうした課題に対応する方法として、年末調整システムの導入が注目されています。本記事では、年末調整システムの基本機能や導入メリット、さらに選定や運用時の注意点について詳しく解説します。
目次
年末調整システムの開発会社・製品選びはプロにお任せ完全無料で全国7000社以上から厳選
年末調整システムとは?基本機能を紹介
年末調整システムには様々な機能が備わっており、業務の効率化や正確な作業をサポートしてくれます。以下では、主要な機能について説明します。
●申告書の配布・回収
年末調整システムは申告書を従業員にオンラインで配布し、簡単に回収できる機能です。システムを利用すれば申告書を一括配信し、従業員が入力したデータを効率的に収集できます。配布プロセスが自動化されることで、管理者の手作業が減り、作業時間を短縮できます。
紙ではなくデータで管理できるため回収時や管理もしやすくなります。さらに、ペーパーレス化により、書類の印刷や郵送コストを削減でき、データを電子的に管理することで保管スペースも不要です。このような機能を活用することで、申告書の配布と回収を効率よく進められます。
●税額計算の自動化
給与情報や控除データを取り込み、税額を自動で計算できる機能です。この機能を使うことで、計算ミスを極力防げるでしょう。控除項目や税制が反映された計算が自動で行われるため、計算の手間を省けます。
また、システムのアップデート機能により、最新の法令にも素早く対応ができます。さらに、入力データの自動チェック機能を活用することで、形式や値の誤りを検出して修正を促すことが可能です。この機能により、従業員の入力ミスを防ぎ、計算に必要な情報を正確に収集できます。
●提出状況の管理
提出状況をリアルタイムで確認する機能があり、管理者は申告書の提出済み・未提出の状態を一覧で把握できます。未提出者を特定しやすいため、進捗管理をより効率化できます。
未提出者への自動リマインド通知を利用することで、提出率を上げられるでしょう。この仕組みにより、管理者の手間が減り、業務負担を軽減できます。さらに、ダッシュボード機能を使えば、視覚的な提出状況の確認や、レポートの出力が可能です。進捗の把握やデータ共有が簡単に行え、業務の分析にも役立ちます。これらの機能を活用することで、年末調整業務を効率的に進められます。
●ほかシステムとの連携
年末調整システムのほか、システム連携機能とは、勤怠管理や給与計算ソフトなど、既存の業務システムとデータを共有する仕組みです。年末調整に必要な給与情報や控除データ、勤怠情報を自動的に取り込みます。
企業ごとの運用やシステム環境に合わせて連携設定を調整できるため、既存システムと年末調整システムの間でデータの一元管理が可能です。この仕組みによって、データの整合性が保たれ、年末調整業務に必要な情報のやり取りが効率化できます。
年末調整システムを導入するメリット
年末調整システムの導入により、担当者と従業員の双方に様々なメリットがあります。以下にそれぞれの視点から解説します。
●担当者にとってのメリット
年末調整システムを導入すると、担当者の業務負担を軽減できます。手作業で行っていた申告書の確認や計算を自動化し、作業時間を短縮。税額計算や控除項目の適用判定も、必要なデータをもとに自動で算出されるためミスも防げるでしょう。
ペーパーレス化による郵送コストの削減はもちろん、保管場所もサーバ上になるためスペースも不要になります。データ検索が可能なため、確認が必要な情報にすぐにアクセスできるのもメリットです。
税制改正に対応した機能により、法改正時の作業がスムーズに進みます。毎年見直される税制にも迅速に対応でき、追加作業を最小限に抑えることが可能です。これらの仕組みを活用することで、担当者の業務負担を大幅に軽減できます。
●従業員にとってのメリット
年末調整システムを利用すれば、従業員は紙書類を使わずにオンラインで申告書の入力や提出ができ、作業の手間を大幅に軽減できます。入力ミスを防ぐチェック機能により、正確な申告が可能です。
過去のデータを引き継ぐ機能も備わっており、前年と同じ内容を再入力する必要がない点もメリット。また、進捗状況をリアルタイムで確認できるため、提出漏れを防ぎながら、自分の進行状況を簡単に把握できます。
システムによっては、スマートフォンやパソコンからのアクセスにも対応しており、場所を選ばず手続きを進められる点も魅力です。自宅や外出先からも柔軟に対応でき、忙しいスケジュールの中でも効率的に作業を終えられます。
年末調整システムの種類と選び方
年末調整システムには様々な種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社に合ったシステムを選定することが肝要です。ここでは、システムの種類と選び方を解説します。
●年末調整に特化したシステム
年末調整特化型システムは、年末調整業務に必要な機能に絞ったシンプルな設計が特徴です。申告書のオンライン配布と回収、税額計算の自動化、提出状況の管理といった基本的な機能を利用できます。そのため、中小企業や年末調整業務の効率化を目指す企業に適しています。
操作がわかりやすく、専門知識がなくても簡単に使えるため、初めて導入する企業にも適しています。機能が絞られている分、導入コストを抑えられるのもメリットです。
ただし、年末調整以外の業務と連携する機能は限定的なため、複数の業務を一元化したい場合はほかのシステムと連携できる機能があるかを確認しておきましょう。
●労務管理全般を支えるシステム
労務管理全般をサポートするタイプは、年末調整だけでなく、勤怠管理や社会保険手続き、労働契約管理など、幅広い業務に対応しています。労務データを一元化し、業務全体を効率化できるため、従業員数が多い企業や業務が複雑な企業に向いています。
ただし、システムの規模が大きいため、導入コストや運用に必要なリソースを事前に確認することが重要です。導入前に業務フローを見直し、必要な機能を絞り込むことで、効果的な運用が期待できます。
●給与計算を含むシステム
給与計算機能を統合したシステムは、給与データと年末調整業務を連携して管理できます。これにより、二重入力を避けつつ、データの整合性を保てます。給与計算や賞与の支給データをそのまま年末調整に活用できる点が特徴です。税制改正に対応できる機能があれば、法律を順守した計算が可能です。
このタイプは、給与計算ソフトを既に導入している企業で、年末調整業務も同じプラットフォームで一元管理したい場合に適しています。ただし、給与計算以外の労務管理機能が限定されることもあるため、ほかの業務への対応状況を事前に確認しておきましょう。
●システムを選ぶポイント
年末調整システムを選ぶ際は、以下の視点を参考に検討してください。
-
自社の業務に合った機能を備えているか
-
初期費用や運用費が費用対効果に見合っているか
-
サポート体制が自社に合っているか
-
無料体験版があるか
まず、進捗管理や自動計算機能が業務要件に適しているか、自社の業務フローに必要な機能が含まれているかを確認してください。
次に、従業員数や企業規模に応じた料金プランを選びましょう。初期費用だけでなく、運用コストや契約更新時の条件を事前に確認し、長期的な費用対効果を考慮してください。
さらに、導入後の運用を円滑に進めるためには、サポート体制が整った企業を選ぶことが大切です。特に、初めてシステムを導入する場合は、操作に関する問い合わせやトラブル対応が迅速かつ丁寧に行われるかどうかを確認する必要があります。
無料体験版を活用すると、操作画面の使いやすさや進捗管理・自動計算機能が業務に適しているかを事前に確認できます。従業員の意見やフィードバックを集め、操作性や運用上の課題を把握することで、適切な選択につなげられるでしょう。
年末調整システムの導入と合わせて労務管理システムをご検討中であれば、下記もぜひご覧ください。
年末調整システム導入時の注意点と対策
年末調整システムを導入する際には、費用や運用面で留意すべき点があります。以下に対策を含めて詳しく説明します。
●事前に費用を確認しておく
年末調整システムを導入する際は、初期費用や利用料金を事前に確認しましょう。従業員数に応じた課金体系や基本料金に加え、オプション機能にかかる費用を含めて総額を把握するのがポイントです。クラウド型システムでは初期費用を抑えられる場合が多い一方で、月額費用や追加サービス料金が別途必要となるケースがあります。
具体例として、従業員50人規模の企業の場合、1名あたりの基本料金が月額5,000円、オプション機能(進捗管理やリマインダー送信)が月額2,000円かかると、1人あたりにかかる年間費用は84,000円。全従業員分を合計すると、年間費用は420万円です。このように、基本料金だけでなく、利用する機能に応じた費用を見積もることが大切です。加えて、サポートや予想外のトラブル対応にかかる費用も勘案しておくと、予想外の出費を抑えられます。
長期的な費用対効果を考慮し、システムを導入することで得られる業務効率化やコスト削減の効果を具体的に評価しましょう。
●従業員に使い方を説明する
システムをスムーズに運用するには、従業員に使い方の説明が欠かせません。申告書の入力や操作に慣れていない従業員には、わかりやすいマニュアルを用意すると良いでしょう。紙ベースだけでなく、社内ポータルやオンラインで参照できる環境を整えることで、必要な時にすぐ確認できます。
操作に不慣れな従業員にはトレーニングを実施し、実際の画面を使ったデモンストレーションを行うと理解が深まります。問い合わせ窓口を設け、操作に関する質問に対応できる体制を整えると問題解決がスピーディーになるでしょう。
●情報の保護と安全性を確保する
年末調整システムでは、従業員の個人情報を扱うため、情報保護と安全性の確保が重要です。システムを選ぶ際は、データの暗号化機能やアクセス権限の設定が適切に備わっているかを確認してください。提供企業のセキュリティ対策が信頼できるかも確認が必要です。
データ暗号化では、申告書の内容や個人情報が外部に漏洩しないよう、通信経路や保存データに暗号化技術(SSL/TLS)が適用されているかをチェックしましょう。アクセス権限の設定では、データを操作できるユーザーを制限し、管理者と一般ユーザーの権限を分ける仕組みの有無を確認しましょう。
クラウド型では、セキュリティ更新が自動で行われるのが一般的です。更新頻度や内容を確認し、過去のセキュリティ事故対応実績を調べることで、提供企業の信頼性を判断できます。
●導入スケジュールを調整する
システムの導入スケジュールは、業務への影響を抑えるため、慎重に計画しましょう。業務が集中する繁忙期を避け、余裕を持って試験運用を開始することで、トラブルを事前に防ぐことが可能です。試験期間中にはシステムの操作性や実務での適合性を確認し、本格導入前に改善点を明確にします。
試験運用中のフィードバックを活用するだけでなく、本格導入後も利用状況を定期的に確認するのがポイントです。従業員の操作頻度や課題を把握し、不慣れな従業員には追加のトレーニングを提供する、問い合わせが多い内容をマニュアルに反映する、などの対応を行うことで、運用の円滑化が図れます。
年末調整システムで業務を一歩先へ
年末調整システムの導入は、担当者と従業員双方にとって業務効率化や負担軽減につながります。システムには、年末調整特化型、労務管理全般を支援する包括型、給与計算を統合したものなど多様であり、それぞれの特性を理解して選定することが重要です。
導入時には、費用の明確化、従業員への説明、情報保護、スケジュール調整といった準備が求められます。これらを踏まえた選択により、円滑な運用が可能です。
発注ナビでは、企業のニーズに合わせた年末調整システムを開発できるベンダーやメーカーを数多くご紹介しています。「自社に合った開発会社がわからない」「選定にできるだけ時間をかけずに順当に導入したい」とお考えのご担当者様は、ぜひ一度発注ナビの利用をご検討してみてはいかがでしょうか。
システム開発の最適な発注先をスムーズに見つける方法
システム開発会社選びでお困りではありませんか?
日本最大級のシステム開発会社ポータルサイト「発注ナビ」は、実績豊富なエキスパートが貴社に寄り添った最適な開発会社選びを徹底的にサポートいたします。
ご紹介実績:27,500件(2025年10月現在)
外注先探しはビジネスの今後を左右する重要な任務です。しかし、
「なにを基準に探せば良いのか分からない…。」
「自社にあった外注先ってどこだろう…?」
「費用感が不安…。」
などなど、疑問や悩みが尽きない事が多いです。
発注ナビは、貴社の悩みに寄り添い、最適な外注探し選びのベストパートナーです。
本記事に掲載するシステム会社以外にも、最適な開発会社がご紹介可能です!
ご相談からご紹介までは完全無料。
まずはお気軽に、ご相談ください。 →詳しくはこちら
年末調整システムの開発会社・製品選びはプロにお任せ完全無料で全国7000社以上から厳選
■年末調整システムに関連した記事