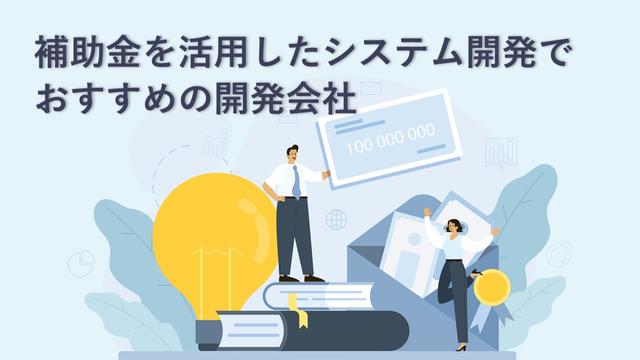AI(人工知能)技術を導入する際に活用できる「AI補助金」について詳しく解説します。AIの開発や導入には多くの費用がかかりますが、国や自治体の補助金をうまく利用すれば、コストを大幅に抑えることができます。本記事では代表的な補助金制度や申請の流れ、活用する際の注意点を具体的に紹介します。AI導入を検討している企業の皆さまは、ぜひ参考にしてください。
目次
AI開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国7000社以上からご提案
AI開発に活用できる補助金とは?
AI(人工知能)技術は企業の競争力を高め、新たな価値を創出するうえで欠かせない存在となっています。ただ、AIの導入や開発を進めるには高度な技術力や知識だけでなく、多額の資金が必要になる場合が多いため、特に中小企業やスタートアップなどでは初期投資が大きな負担になりがちです。そこで利用を検討したいのが、国や自治体などが提供している各種補助金です。うまく活用すれば、AI導入費用の一部を軽減できるため、事業を円滑にスタートさせることが期待できます。
ただし、補助金には申請条件や用途、事前提出書類などの要件が細かく定められていることが多く、自社の事業内容に合ったものを探し、しっかりとした計画や書類を準備しなければいけません。また、補助金によっては生産性の向上や新サービス開発など、AIをどのように活用するかまで問われることがあります。こうした要件を踏まえた上で、自社に最適な補助金を見極め、採択されるためのポイントを押さえることが大切です。
ここからは、代表的な補助金の種類や申請の流れ、注意点を順に解説していきます。自社のAI導入・開発計画に合う補助金を見つけるための参考にしていただき、事業の成長を加速させる手立てとしてお役立ていただければ幸いです。
代表的なAI開発向け補助金の種類
AI活用の推進を後押しする制度は国や地方自治体などから数多く用意されています。中でも広く知られる代表的な補助金として、IT導入補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、中小企業新事業進出補助金、さらに融資の形態としてAI活用融資(日本政策金融公庫)などが挙げられます。これらは企業規模や事業内容によって対象となる枠や要件が異なり、目的とするAI活用の形によっても適用可否が変わってきます。それぞれの特徴を理解したうえで、自社の計画に合った制度を選ぶことが補助金活用成功の近道といえるでしょう。
●IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者などが自社の生産性向上や業務効率化を図るためにITツールを導入する際、その費用の一部を補助してくれる制度です。AI技術を用いたソフトウェアや業務改善ツールの導入にも適用が可能な場合がありますが、対象となるITツールはあらかじめ事務局による審査・登録を受けたものに限られる点が重要です。
さらに、申請には「IT導入支援事業者」と呼ばれる登録ベンダーと連携し、導入計画を一緒に作成する必要があります。これらの支援事業者は、補助金の申請手続きだけでなく、具体的なシステム導入やその後の運用サポートまで幅広い支援を行うため、導入前にしっかり相談しておくと安心です。
補助率や上限額は、企業の業種や規模、導入ツールのプロセス数、申請する枠(通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠など)によって異なります。例えば通常枠では補助率1/2(最低賃金近傍の事業者は2/3)で、導入するITツールの種類やプロセス数に応じて、補助金は5万円から最大450万円まで設定されることがあります。一方、インボイス制度への対応を目的とした会計ソフトの導入などを支援する枠では、補助率が4/3や5/4などに設定される場合もあり、申請条件や補助金額がさらに細分化されているのが特徴です。
| 申請枠 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 1/2以内(最低賃金近傍の事業者:2/3以内) | 5万円~450万円(ITツールのプロセス数による) |
| インボイス枠(インボイス対応類型) | 中小企業:4/3以内(50万円以下)、2/3以内(50万円超~350万円以下) 小規模事業者:5/4以内(50万円以下)、2/3以内(50万円超~350万円以下) |
50万円または350万円 |
| インボイス枠(電子取引類型) | 2/3以内 | 350万円 |
| セキュリティ対策推進枠 | 1/2以内(小規模事業者:2/3以内) | 5万円~100万円 |
| 複数社連携IT導入枠 | 1/2以内(連携する中小企業・小規模事業者の数による) | 3,000万円(連携する中小企業・小規模事業者の数による) |
●ものづくり補助金
ものづくり補助金は、正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といい、革新的な製品開発や生産プロセスの改善に向けた設備投資などを支援する制度として広く活用されています。AIを使った生産ラインの自動化や効率化を目的とする取り組みなども、高い付加価値が見込まれる場合は申請対象になる可能性があります。
申請時は、AI導入による生産性向上やサービス改善の具体的な計画を3~5年スパンで示す必要があります。また、従業員の賃上げに取り組むといった条件を満たすことも要件の一つとなりやすく、採択されるための計画作りには一定の時間と労力を要します。補助率は通常1/2ですが、小規模事業者や再生事業者なら2/3といった優遇がある場合もあり、従業員数や申請枠によって補助上限額が750万円から2,500万円、さらに賃上げの度合いによっては3,500万円や3,000万円を上回る場合もあります。
| 申請枠 | 従業員数 | 補助上限額 | 補助上限額(大幅賃上げ特例適用時) | 補助率 |
|---|---|---|---|---|
| 製品・サービス高付加価値化枠 | 5人以下 | 750万円 | 850万円 | 中小企業 1/2、小規模・再生 2/3 |
| 6~20人 | 1,000万円 | 1,250万円 | 中小企業 1/2、小規模・再生 2/3 | |
| 21~50人 | 1,500万円 | 2,500万円 | 中小企業 1/2、小規模・再生 2/3 | |
| 51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 | 中小企業 1/2、小規模・再生 2/3 | |
| グローバル枠 | 全従業員数 | 3,000万円 | – | 中小企業 1/2、小規模事業者 2/3 |
参照:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金|全国中小企業団体中央会
●小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模企業や個人事業主などが販路開拓や業務効率化を目的とした取り組みを行う際に活用できる制度です。企業規模は商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)で従業員5人以下、それ以外の業種で20人以下といった要件が設けられており、マーケティングツールや顧客管理システムなどAIを活用した施策が補助対象として認められるケースがあります。
申請の際には、地域の商工会議所や商工会からの支援を受けて、経営計画書や補助事業計画書を作成し、「事業支援計画書」を交付してもらう必要があります。上限額は通常枠で50万円ですが、賃金引上げに取り組むなどの特定要件を満たすと最大200万円になることもあります。また、インボイス特例などの適用により、さらに上乗せされるケースもあるため、制度ごとの詳細を確認しながら必要書類を整えるとよいでしょう。
| 申請枠 | 補助率 | 補助上限額 | インボイス特例(上限上乗せ) |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 2月3日 | 50万円 | 50万円 |
| 賃金引上げ枠 | 2/3(赤字事業者:3/4) | 200万円 | 50万円 |
| 卒業枠 | 2月3日 | 200万円 | 50万円 |
| 後継者支援枠 | 2月3日 | 200万円 | 50万円 |
| 創業枠 | 2月3日 | 200万円 | 50万円 |
| 共同・協業型(新設) | 参画事業者:2/3、地域振興等機関:定額 | 5,000万円 | – |
| ビジネスコミュニティ型(新設) | 2月3日 | 200万円(特定要件該当者は500万円) | 50万円 |
| 災害支援枠 | 2月3日 | 直接被害:200万円、間接被害:100万円 | – |
●中小企業新事業進出補助金
中小企業新事業進出補助金は、2025年から始まる新しい補助金制度です。既存事業とは異なる新規事業や、新たに高付加価値化を狙う投資などに適用できるのが特徴で、AIを使った新しいサービスを開発したい場合や、まったく異なる市場へ参入する際の設備投資などが支援される可能性があります。単なる事業の延長線上ではなく、新事業への進出が明確であることが採択のポイントとなりやすいと考えられます。
補助率は原則1/2ですが、小規模事業者や大幅な賃上げを行う事業計画を策定した場合には2/3に引き上げられる見込みです。さらに、企業の従業員数に応じて補助上限額が2,500万円から7,000万円まで設定され、賃上げ要件を満たすと最大9,000万円といった特例も設けられています。下限額は750万円で、比較的大規模な投資を行う中小企業の新事業創出に向いている制度といえます。
| 従業員数 | 補助上限額 | 補助上限額(大幅賃上げ特例適用時) | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 20人以下 | 2,500万円 | 3,000万円 | 1/2 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 | 1/2 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 | 1/2 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 | 1/2 |
| 小規模事業者等 | 上記に準ずる | 上記に準ずる | 2/3 |
| 賃上げ要件達成 | 上記に準ずる | 上記に準ずる | 2/3 |
●AI活用融資(日本政策金融公庫)
AI活用融資は日本政策金融公庫が行っている融資制度であり、補助金とは異なる形でAI導入を資金面から支援する仕組みです。返済義務のある融資ですが、金利の優遇措置が設けられているため、自己資金が不足している企業にとっては検討の価値があります。
設備投資だけでなく、AI導入にともなう運転資金として利用できる点がメリットです。ただし、具体的なAI導入計画と、経済産業省が認定する「スマートSMEサポーター」の専門家から助言を受けていることなどが融資条件として求められます。また、後述するように、融資であっても審査のための書類作成や資金計画の立案は必要となるため、十分に準備をして臨むことが大切です。
補助金申請の流れ
AI開発に活用できる補助金の申請手続きは、補助金ごとに異なる部分があります。しかし、大まかな流れとしては多くの制度で共通点があり、事前準備の不足による書類不備などで審査に通らなくなるリスクは避けたいところです。ここでは、一般的な手順を5つのステップに分けてご紹介します。
●①情報収集と適用補助金の選定
まず重要なのは、自社が取り組もうとしているAI開発・導入計画に合った補助金を探す作業です。補助金ごとに対象となる企業規模や事業内容、経費区分などの条件が細かく設定されているため、公式サイトや省庁の公募要領、自治体の窓口情報などを活用して最新の情報を収集し、該当する補助金を絞り込みます。加えて、募集期間や申請締切が早まる場合もあるため、興味を持ったらできる限り迅速に申請スケジュールを調べ、早めの準備を心がけることが肝心です。
●②事業計画の作成
補助金の審査で重視されるのが、AI導入によってどのような効果が得られるかを明確に示した事業計画書です。例えば、生産性がどれだけ向上するのか、売上や利益にはどの程度寄与する見込みがあるのか、導入後の具体的な運用体制はどうなるのか、といった点が審査の重要な着眼点になります。また、補助金によっては従業員の賃上げ計画や市場拡大の可能性などを加味することもあります。こうした要件を踏まえた上で事業計画を作り込み、申請書に分かりやすく落とし込む必要があります。
●③申請書類の準備と提出
事業計画書以外にも、会社概要(登記簿謄本や納税証明書など)、財務諸表、見積書、導入予定のAIシステムに関する資料など、多くの書類が必要となります。書類の記入にミスや漏れがあると審査に影響が出る場合があるため、記載事項を丁寧に確認しながら取り組みましょう。電子申請が必須となっている補助金も多く、GビズIDプライムなどのアカウント準備が必要になる場合があります。こうした事務的な手続きだけでも時間を要するため、早め早めの行動を心がけると安心です。
●④審査と結果通知
書類を提出した後は、事務局や専門家による審査が行われます。AI関連の補助金の場合、単なるITツールの導入だけでなく、具体的にどのようにAIを活用して生産性向上や業務効率化、新しい付加価値の創造に貢献するかを審査されることが多いです。審査は複数段階にわたるため、結果通知まで一定の期間がかかることを見越してスケジュールを立てておくとよいでしょう。採択の可否はメールや公募サイトなどで通知され、採択となれば補助金交付手続きに進みます。
●⑤事業実施と実績報告
採択された後は交付決定通知を受け取り、実際にAI導入・開発を行います。多くの補助金は後払い方式のため、まずは自己資金や融資で必要経費を立て替える形になります。事業期間中は領収書や契約書など経費証拠となる書類を正確に保管し、補助対象と自己負担分を明確に区分しておくことが大切です。事業完了後には実績報告書を提出し、審査を経て最終的に補助金が支給されます。報告の内容に不備があると補助金を満額受け取れないこともあるため、細心の注意を払いながら取り組む必要があります。
補助金活用の注意点
補助金は企業にとって心強い支援策ですが、その特性を誤解したまま進めると、かえってリスクを負う場合もあります。ここでは、補助金を活用するにあたって知っておきたい注意点を整理します。
●申請条件を事前に確認
補助金には必ず対象となる業種や事業規模、事業内容が定められています。AI関連の補助金であっても、「製造業の革新的技術開発が対象」「ITツールが登録済みのものに限る」など、細かな条件があるため、自社の事業内容が本当に合致するのかを事前に確認する作業は欠かせません。公式サイトや公募要領の最新情報を入手し、自社の計画を丁寧に照らし合わせるようにしましょう。
●後払い方式のため資金繰りを考慮
多くの補助金は後払い(精算払い)が基本であるため、事業の開始時点で必要となる費用を自己資金や銀行融資などで賄わなくてはなりません。補助金が採択されたとしても、実際に入金される時期は事業完了後であり、その間のキャッシュフローに問題が生じるケースもあります。余裕をもった資金計画を立て、補助金はあくまで“最後に支給されるもの”と考えると、実務でのトラブルを避けられます。
●申請期限と書類の準備
補助金には必ず募集期間や申請期限があり、期限を過ぎると申請自体が認められません。また、申請書類の不備や不足資料があると審査対象外になってしまうこともあるため、ギリギリのスケジュールで進めるのは非常にリスクが高いです。締切のかなり前から必要書類をリスト化し、余裕を持って一つずつ準備する姿勢が大切だといえます。
●補助金の対象経費を確認
AI開発や導入に関連するといっても、すべての経費が補助対象になるわけではありません。制度によってはソフトウェア購入費は対象になる一方、PC本体の購入費や汎用的なオフィス機器の費用は補助対象外になる場合があります。自社が予定している経費の中でどこまでが認められるのかをしっかり確認し、計画と実際の支出に乖離が生じないように注意しましょう。
●補助金申請のサポートを活用
補助金の申請手続きは複雑で、初めて取り組む場合には戸惑うことも多いでしょう。商工会議所や行政書士、中小企業診断士といった専門家がサポートを行っており、補助金の公募要領の読み解き方から事業計画の作成方法、書類の書き方など、幅広く助言が受けられます。また、有料のコンサルティングサービスを利用する企業も増えており、専門家の力を借りることで採択率が上がる可能性があります。自社内のリソースやノウハウが限られている場合は、上手に外部の知見を活用することが成功への近道です。
AI開発のコストを抑えて事業を加速させよう
AIを活用したシステムやサービスを開発しようとすると、多くのケースで設備投資やソフトウェア導入、人材育成などにまとまった費用がかかります。ただ、ここまでご紹介したように、国や自治体が用意している補助金制度を賢く使えば、そうした費用負担を軽減しながら事業を進めることが可能です。
ただ、補助金ごとに特徴や申請条件が違うため、自社の事業計画にぴったり合う制度を探すことが不可欠でしょう。適切な補助金を選定し、計画的に申請の準備を進めれば、AI導入による競争力の強化や事業の拡大をぐっと後押しできます。新事業立ち上げや高度なAI活用を検討している企業の皆様は、ぜひ上記の情報を参考にしながら、自社に合う制度を見つけて活用してみてはいかがでしょうか。
発注ナビでは、企業のニーズに合わせた工数管理ツールを開発できるベンダーやメーカーを数多くご紹介しています。「自社に合った開発会社がわからない」「選定にできるだけ時間をかけずにスムーズに導入したい」とお考えのご担当者様は、ぜひ一度発注ナビの利用をご検討してみてはいかがでしょうか。
AI開発の最適な発注先をスムーズに見つける方法
AI開発会社選びでお困りではありませんか?
日本最大級のシステム開発会社ポータルサイト「発注ナビ」は、実績豊富なエキスパートが貴社に寄り添った最適な開発会社選びを徹底的にサポートいたします。
ご紹介実績:26,500件(2025年8月現在)
外注先探しはビジネスの今後を左右する重要な任務です。しかし、
「なにを基準に探せば良いのか分からない…。」
「自社にあった外注先ってどこだろう…?」
「費用感が不安…。」
などなど、疑問や悩みが尽きない事が多いです。
発注ナビは、貴社の悩みに寄り添い、最適な外注探し選びのベストパートナーです。
本記事に掲載するシステム会社以外にも、最適な開発会社がご紹介可能です!
ご相談からご紹介までは完全無料。
まずはお気軽に、ご相談ください。 →詳しくはこちら
AI開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国7000社以上からご提案