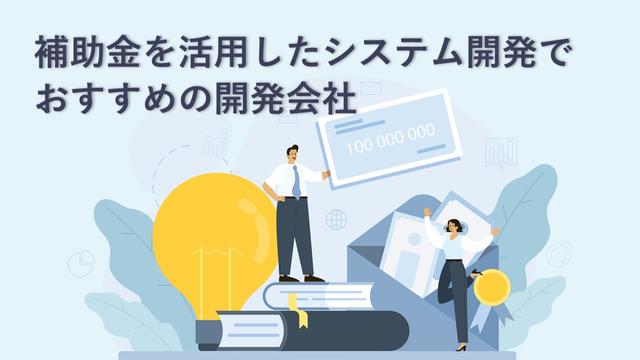訪日外国人旅行者の増加とともに、小売・観光業にとって「免税対応」は重要な施策となっています。特に2021年の免税手続き電子化義務化、さらに2026年に予定されている「リファンド方式」の導入により、販売管理のあり方は大きな転換期を迎えています。
この記事では、最新制度への対応に必要な販売管理システムの機能や導入メリット、店舗規模に応じた選び方、補助金の活用方法まで、具体的に解説します。
目次
販売管理システム・開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国7000社以上から厳選
販売管理システムで免税対応する重要性
2021年10月以降、免税販売を行うすべての事業者には、免税手続きの電子化に対応することが義務付けられました。紙での購入記録票や誓約書が原則認められなくなったため、訪日外国人旅行者のインバウンド需要を取り込むうえでも、デジタル化された免税手続きに対応できる販売管理システムの整備は避けて通れない課題といえます。さらに、2026年11月には「購入時に課税し、出国時に返金する」という新しい免税制度(リファンド方式)が導入される予定があり、これに合わせたシステム対応も視野に入れて準備を進める必要があります。
●販売管理システムとの連携が重要
免税手続きに対応するシステムを単独で運用するよりも、既存の販売管理システムやPOSレジなどと統合することで、業務効率を大幅に高めることができます。通常の販売データに加えて免税情報を一元管理できるようになれば、商品マスタ管理や在庫管理、会計処理などと連動して、売上計上をスムーズに行いやすくなります。レジ画面でパスポート情報を読み取り、免税対象商品の判定や消費税率の適用可否が自動化されれば、スタッフの手入力ミスや二重入力による不整合を防ぎ、業務全体の精度が向上します。
さらに、多言語表示に対応したレジ画面や顧客案内システムを導入すれば、訪日外国人旅行者とのコミュニケーションがスムーズになり、接客の満足度アップに貢献しやすくなります。免税制度への対応を単なる義務としてとらえるのではなく、販売管理システム全体を見直すきっかけと捉えることが、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進にもつながっていくでしょう。
●これから免税を始める店舗にこそ導入を検討してほしい
これから免税販売を新しく始める事業者は、税務署への申請手続きや店ごとの識別符号取得など、準備すべきことが多く存在します。具体的には、輸出物品販売場許可申請書や購入記録情報の提供方法等の届出書を提出して、店舗ごとに固有の識別符号を取得しなければなりません。
こうした手続きは初めて免税販売に挑戦する店舗にとっては複雑ですが、近年では免税システムを提供するベンダーや承認送信事業者が、申請代行や導入支援サービスを行っているケースが増えています。税理士によるサポートが受けられるところもあるため、専門家の知見を活用すればスムーズに店舗を立ち上げやすくなるでしょう。特にスタッフ数が限られた小規模店舗では、免税手続きの大部分をシステムで自動化し、人的な事務作業を削減する効果が大きく期待できます。最近はスマートフォンやタブレットを活用した低コストの免税アプリも登場しており、以前に比べて導入のハードルは下がっています。
免税電子化に求められるシステム要件とは
免税販売の電子化が進む中で、販売管理システムやPOSシステムには具体的な機能要件が求められるようになっています。以下では、その代表的な要素について紹介します。
●パスポート情報の読み取りと記録
免税販売では、購入者が免税対象者(非居住者)であるかを確認する必要があり、その確認にはパスポート情報を電子的に取得する機能が必須です。もし手入力で情報を登録しようとすると、入力ミスが起きやすいうえ、混雑時の対応に時間がかかりすぎてしまいます。
OCR機能付きカメラや専用のパスポートスキャナが用意されているシステムであれば、旅券番号や氏名、国籍、生年月日などを瞬時に読み取り、システムへ取り込むことが可能です。これによって、来店客の待ち時間が短縮されるだけでなく、データの正確性も向上します。データに誤りがあると、国税庁への送信や税関での確認時に問題が起こる可能性があるため、信頼性の高い読み取り機能を備えたシステムを選ぶことが肝心です。
●免税対象商品の管理
免税対象になる商品は「一般物品」と「消耗品」に分かれ、それぞれ最低購入金額や包装要件が異なるなど複雑なルールが存在します。ただし、2026年11月のリファンド方式導入にともない、こうした区分や特別な包装要件が将来的に撤廃される予定です。いずれにしても、現行制度への対応としては、商品ごとに免税区分を登録し、レジ操作時に自動判定できる仕組みがあると便利でしょう。
購入金額が最低免税金額(現在は税抜5,000円以上)を満たしているかどうかをシステムが自動で判別してくれる機能も、担当者の判断ミスを防ぐうえで重要です。さらに、どのお客様がどの商品をいつ購入したかを正確に保存・管理し、国税庁へ送るための購入記録情報を作成する流れがシステム上で完結すれば、作業が飛躍的に効率化します。
●国税庁との連携機能
免税販売データは、インターネット回線などを通じて国税庁へ送信する必要があります。販売後すぐ、または遅滞なく送信できるシステムでなければ、旅行者が出国する際に税関がそのデータを確認できず、免税と認められなくなるリスクが生じます。通信手段としてはインターネット回線が一般的ですが、セキュリティレベルを高めるためにIP-VPN回線を採用する事業者もあります。
また、送信するデータにはパスポート情報などの個人情報が含まれるため、クライアント証明書の導入や通信経路の暗号化など、適切なセキュリティ対策を行っていることが不可欠です。自社送信と他社送信のいずれを選ぶ場合でも、接続テストやセキュリティ要件をクリアできるかをよく確認する必要があります。
リファンド方式に向けた販売管理の対応
2026年11月に本格導入が予定されているリファンド方式は、現行の免税制度から大きく仕組みが変わります。この変化に対応するためには、販売管理システムも新たな機能を備えておくことが求められます。
●「リファンド方式」とは?
リファンド方式は、店頭で消費税込みの金額を支払い、旅行者が出国時に商品を携行していることを税関が確認したうえで、後から消費税を返金する制度です。不正な免税を防ぐねらいがあり、実際に持ち出された物品だけが免税の対象になるため、店舗側には出国後の確認データを取り込んで返金処理を行う手順が加わります。
この制度では、免税店が購入記録情報と税関の確認結果を突き合わせ、返金対象かどうかを判断しなければなりません。つまり、販売時と出国後の二段階でシステムが機能する必要があり、データ管理がより複雑化することが想定されます。
●システムに必要となる機能とは
リファンド方式では、税関から「この取引は持ち出し確認が取れた」「取れなかった」といったステータス情報を受け取り、購入データと照合する仕組みが求められます。具体的には、API連携による「Pull型」で定期的に確認結果を取得し、該当する取引を免税確定(=後日返金対象)か、それとも課税扱いで確定かをシステム上で更新する流れです。
出国確認が取れない取引については、課税販売として確定しておく必要があります。一方、確認が取れれば返金処理を行い、最終的な取引ステータスを免税扱いとするわけです。こうした双方向のデータ連携に対応し、取引ステータスの変更履歴を7年間保存する機能まで含めて整備しておかないと、後々の監査やトラブル対応が困難になります。
免税販売システムにおける送信方式の選び方
免税手続きの電子化対応では、国税庁への購入記録情報の送信方式を「自社送信」にするか「他社送信(承認送信事業者に委託)」にするかを決めなければなりません。それぞれにメリットとデメリットがあるため、店舗の規模やITリソースに応じて選択すると良いでしょう。
●自社送信か、他社送信か
自社送信は、自前のシステムを国税庁の免税販売管理システムにつなぐ方法です。導入・保守のコストやセキュリティ対策は自社負担となる反面、月額手数料を支払わずに済む可能性があり、データを自社主導で管理できる柔軟性があります。一方で、IT部門の人的リソースが乏しい場合は負担が大きいでしょう。
他社送信では、国税庁の承認を受けた「承認送信事業者」が代行してくれるため、導入のハードルが低く、セキュリティ管理なども任せやすいメリットがあります。ただし、システム利用料や取引ごとの手数料が発生する場合が多く、将来的に事業者を切り替える際はデータの引き継ぎや国税庁への届出変更などが必要になる可能性があります。
以下のような比較表を参考にすると、自社に合った方式を選ぶ目安になります。
| 特徴 | 自社送信 | 他社送信 |
|---|---|---|
| 導入・開発コスト | 社内でシステム構築が必要、初期費用高め | 事業者のサービスを利用、初期費用低め |
| 運用コスト | 月額利用料や従量課金は抑えやすい | 月額・従量課金などが発生するケースが多い |
| システム管理 | 自社ですべて管理・保守 | 事業者が保管・送信を代行 |
| セキュリティ | 電子証明書の管理や暗号化に自社責任 | 基本的に事業者側が責任を持つ |
| 適したケース | 大規模店やIT部門を持ち、運用の自由度を重視 | 小規模店やIT人材不足で導入を簡単にしたい |
●送信方式選定のポイント
社内に専門のシステム担当者がいなければ、他社送信のほうがスムーズです。逆に、長期的なコスト削減や自前の基幹システムとの連携に強いこだわりがある企業は自社送信を選ぶ傾向にあります。店舗の規模、免税取引のボリューム、予算、将来的なリファンド方式への拡張などを総合的に考慮して選ぶことが大切です。
なお、どちらを選ぶ場合でも、2026年のリファンド方式導入に向けた対応状況やアップデートの計画をベンダーに確認しておくと安心できます。特に他社送信の場合は、その事業者が今後どのように機能改修を進めていくのか、明確なロードマップを示してくれるかをチェックすることが重要です。
導入の際は補助金の活用も検討
免税対応のために販売管理システムを改修・導入するには、ある程度の費用負担が発生します。とくに中小規模店舗にとっては、このコスト面がネックになることも少なくありません。そこで、国や自治体が提供する補助金制度を活用する方法があります。
●導入を後押しする支援制度がある
たとえば「IT導入補助金」や「インバウンド受入環境整備高度化事業」、「小規模事業者持続化補助金(インボイス・免税対応枠)」など、条件を満たせば免税システムや関連するPOSレジの導入費用を部分的に補助してもらえる可能性があります。制度名や公募時期、補助対象の範囲は随時変わるため、最新の公式情報を確認しつつ検討することが必要です。
以下に一例として、補助金を比較した表を示します。実際に申請する際には、それぞれの窓口にお問い合わせください。
| 補助金名(例) | 対象者(例) | 主な目的・対象経費(例) | 注意点(例) |
|---|---|---|---|
| インバウンド受入環境整備高度化事業 | 観光関連事業者など | 訪日客受入を強化するIT施策(免税システム導入など) | 公募時期・補助率が都度変動。詳細は公式情報を要確認 |
| IT導入補助金 | 中小企業・小規模事業者 | ソフトウェア購入費、導入関連費など(POSレジや販売管理システム等) | 事前登録されたITツールが対象。申請枠により要件が異なる |
| 小規模事業者持続化補助金 (インボイス・免税対応枠) |
小規模事業者 | 販路拡大や制度対応に必要な経費 (免税電子化やインボイス対応など) |
商工会議所・商工会との連携必須。後払い方式が基本 |
●補助金を活用する際の注意点
補助金を活用する場合、申請には審査があるため必ず採択されるとは限りません。また、補助金の支給は後払いになる場合が多いので、いったん自己資金で立て替える必要があります。加えて、対象システムや導入事業者が限定されるケースもあるため、自社が導入したいシステムが補助金の要件に合致するか必ず事前に確認してください。
システム導入は長期的な投資となるため、「補助金があるから」といって急いで決めずに、自社のニーズを十分に検討したうえで最適なシステムを選び、その後に適用できそうな補助金を探すのがおすすめです。公募期間や詳細要件は年度によって変わるので、常に最新情報にアンテナを張っておくとよいでしょう。
今こそ、免税販売対応の準備を始めるタイミング
免税制度は2021年10月の電子化義務化に続き、2026年11月のリファンド方式導入によってさらに変化していきます。時間があるように見えても、システムの見直しや導入には想像以上の期間がかかることも多いため、早めに準備を始めることが重要です。
制度変更が連続して予定されている今こそ、販売管理システムが最新の免税要件を満たしているか、将来的なリファンド方式への拡張性をもっているかを確認してみてはいかがでしょうか。特に新型コロナウイルス感染症の影響からインバウンド需要が徐々に回復しているいま、訪日客への対応を強化しておけば、店舗の売上増にもつながりやすくなります。
まずは現在使用しているPOSや販売管理システムが免税に対応できているかをベンダーに問い合わせたり、資料請求して詳細を確認したりするところから始めると良いでしょう。外部のシステム開発会社や承認送信事業者に相談すれば、手続きの進め方や補助金の使い方もアドバイスしてもらえるため、スムーズに導入計画を立てられます。
発注ナビでは、企業のニーズに合わせた販売管理システムを開発できるベンダーやメーカーを数多くご紹介しています。「自社に合った開発会社がわからない」「選定にできるだけ時間をかけずにスムーズに導入したい」とお考えのご担当者様は、ぜひ一度発注ナビの利用をご検討してみてはいかがでしょうか。
販売管理システム・開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国7000社以上から厳選