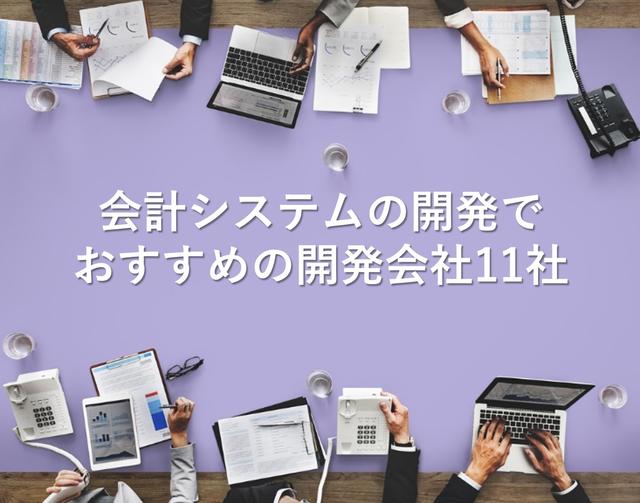会計システムは、経理業務を簡易化することによってヒューマンエラーや作業工数を削減し、業務を効率化できるシステムです。これまでExcelなどで会計処理を行ってきたけれど、会計業務の効率化を目指して会計システムの導入を検討している、という方も多いのではないでしょうか。
しかし、会計システムには、数多くの種類がリリースされており、どれを選ぶべきか悩むことも少なくありません。また、自社でオリジナルの会計システムを導入する場合、どの程度の費用が必要になるのか確認したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、会計システムの費用相場や見積もり方法、選び方などについて詳しく解説します。
目次
システム開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国6000社以上からご提案
会計システムとは?
会計システムとは、企業の会計業務をシステム化することで、帳票などの作成作業、帳票の連携などを行えるシステムのことを指します。従来、伝票を作成して帳簿に転記して、試算表を作成し、さらに決算書の作成や経営分析、管理などを手動で行っていました。会計システムは、今まで手動で行っていた作業を、データとして一元化することによって、会計業務を効率化できるシステムです。そもそも会計にかかわる作業は手間がかかり、ミスが発生しやすい傾向にありました。企業にとって重要である会計業務のミスを削減し、効率的に進めるために、多くの企業で会計システムが導入されるようになりました。会計システムに関する詳しい内容は、「会計システムの機能とは?導入前に知っておきたいメリットとリスク」で解説しています。ぜひご覧ください。
「導入費用」と「運用費用」について
会計システムを導入する際に必要になる費用は、「導入費用」と「運用費用」の2つの種類に分けられます。導入費用とは、その名のとおり会計システムを導入する際にかかる費用のことであり、会計システムのソフトウェアを購入するための費用を指します。一般的なソフトウェアの場合、購入後に継続して費用が必要になることはありません。しかし、会計システムの場合は、会計にまつわる法律が定期的に見直され、変更が加わるため、導入費用以外にも運用費用がかかる場合もあります。改正の内容に従ってアップデートしたり、機能を追加変更したりすることがあるため、数多くの会計システムにおいて導入費用とは別に運用費用が必要になる仕組みです。買い切りモデルの会計システムもありますが、法改正があった場合には翌年には同じシステムが使えなくなる可能性があるため、注意が必要です。
会計システムを導入する際に必要な費用
会計システムは、大きく分けると「インストール型の会計システム」と「クラウド型の会計システム」の2種類になります。ここでは、それぞれのシステムの特徴や費用相場についてご紹介します。
●インストール型(パッケージ型)
インストール型の会計システムは、パッケージ化されているソフトを購入して、使用する端末にインストールするタイプのシステムです。パッケージで購入することから、パッケージ型とも呼ばれていますが、ここではインストール型として解説します。インストール型の特徴は、インストールした端末でしか使用できないことが挙げられます。重要な会計情報を固定の端末でのみ編集できるため、セキュリティ面を強化できます。しかしその一方で、社外などから会計情報にアクセスすることが困難な点がデメリットだといえます。
インストール型の費用相場
小規模であれば、Webやパソコンショップでソフトウェアを購入して、自身でインストールできます。また、サービス提供事業者に依頼して、ハードウェアも含めて導入することも可能です。
【導入費用】
市販の会計ソフトは約2万円〜5万円程度で、高くても10万円程度で収まります。サービス提供事業者に依頼して1からシステム構築する場合は、オプションの有無にもよりますが、市販のものと比べて一桁ほど高額になる傾向にあります。詳しくは個別に見積もりを依頼することになります。
【運用費用】
インストール型の場合、サポート費用の名目で月々あるいは年間で費用が必要となります。自身で購入しインストールした場合は年間で数万円程度です。無料ではないため、注意が必要です。システム構築をした場合はやはり一桁ほど高額になるため、個別に見積もりが必要となります。
●クラウド型
クラウド型は、インターネットを利用したタイプのシステムです。データはインターネットを通して保管されるため、インストール型のようにバックアップを取る必要がなく、サービスにアクセスするだけで会計情報を閲覧、編集できるようになっています。インターネットが利用でき、アクセス情報をもっていれば、どの端末からもデータにアクセスできるため、インストール型とは異なり、様々な場所からアクセスが可能です。また、税理士との会計情報の共有にも適しています。
クラウド型の費用相場
【導入費用】
クラウドを利用することによって、導入費用の大半が無料になります。自身でインストールする必要もなく、即日での使用が可能です。
【運用費用】
インストール型と異なり、クラウドでは月々の使用量が必要になります。個人や小規模企業の場合、1万円〜5万円程度となります。クラウド型が低コストとは限らないため、注意が必要です。長期間使うことを想定した場合、インストール型のほうが低コストな傾向にあります。ただし、クラウドは所有しないという特徴から、資産として計上する必要がありません。また、将来にわたって費用の予測が簡単になるため、投資計画が立案しやすいというメリットもあります。
会計システムの選び方
会計システムを導入する際の選び方には、以下の5つのポイントが挙げられます。それぞれのポイントについて、詳しくご紹介します。
-
自社の業務内容にマッチする機能が搭載されているか
-
UIが見やすく操作が簡単か
-
ほかシステムとの連携は可能か
-
自社の規模や従業員にマッチするシステムか
-
税制度変更や法改正に自動対応しているか
●自社の業務内容にマッチする機能が搭載されているか
会計システムを選ぶ際に、最も重要なポイントは「自社の業務内容にマッチする機能が搭載されているか」という点です。例えば、「通帳の記帳や仕訳の入力の作業効率」が課題なのであれば、手入力が必要な会計システムはマッチしません。 導入前の自社の現状や課題を明確にし、それらを解決してくれる機能が搭載されている会計システムを選びましょう。自社に適した会計システムを導入することによって、会計業務の効率化だけでなく経営状況の把握も可能になります。
●UIが見やすく操作が簡単か
「UIが見やすく、操作が簡単か」ということも、重要なポイントの1つです。会計システムを導入した際に、操作が難しかったりUIが見にくかったりすると、すべての従業員が使いこなすことが困難になることも起こり得ます。そのような状況では、業務の効率化どころか、業務の効率が悪化してしまうことにもなりかねません。誰もが見やすく、使いやすいシステムを選ぶことによって、現場の従業員の負担になることがなく利用でき、引き継ぎ作業もスムーズになります。専門知識がないと使いにくかったり、必要な機能を見つけにくかったりというシステムを選ぶのは避けましょう。また、サポート体制が充実しているかという点にも注意しましょう。システムの利用において不明点が生じた際に、使い方や設定方法などについて直ちに相談できるシステムがおすすめです。
●ほかシステムとの連携は可能か
会計システムとほかのシステムと連携できると、さらに業務の効率化につながります。例えば、金融機関を登録することによって連携できるシステムであれば、入出金明細データ取得の自動化や、AIによる仕訳の自動化が可能になります。また、経費精算システムや勤怠システム、給与計算システムなどのほかのシステムやツールと連携することによって、バックオフィス全体の業務効率化にもつながります。
●自社の規模や従業員数にマッチするシステムか
企業の規模や従業員数といった点も、会計システムを選ぶ際に注意が必要なポイントです。従業員数が30名以下の企業と、従業員数が300人の企業とでは、抱えている課題が異なり、必要な機能も変わってきます。
従業員数が30名以下の企業の大半は、会計業務の専任者は不在で、経営者自ら、もしくは管理部門の担当者が会計、給与、人事などの管理業務をトータルで兼務している傾向にあります。そのため、「会計の専門知識がなくても短期間でスムーズに利用できるか」ということが重要です。例えば、「仕訳入力サポートが充実しているか」や「ほかのバックオフィス業務の効率化につながるか」という点に注意しましょう。
一方で、従業員数が300名の企業においては、営業部門と経理部門とのコミュニケーション・ロスから会計業務が滞ることが起こり得ます。そのため、部署間の壁を超えて関連業務をスムーズに効率化できる機能が必要になります。また、上場企業にとって、会計業務は単なるバックオフィス業務ではなく、監査対象となる重要な業務でもあるため、内部統制に対応したフローの構築が必要になります。
●税制度変更や法改正に自動対応しているか
2023年10月から、インボイス制度が導入されました。こういった税制度の変更や法改正に自動対応しているかということも重要な要素です。Excelなどの表計算ソフトを用いた会計業務においては、法令改正や消費税の増税などがあった際には手入力での各種変更作業が求められました。手入力での変更作業は、時間がかかるだけでなくヒューマンエラーも起こりやすいというデメリットがあります。しかし、税制度の変更や法改正に自動対応している会計システムを選ぶことによって、利用する側の作業が不要になるというメリットがあります。
会計システムを独自開発するという手もある
既製の会計システムでは、企業独自のすべてのニーズに対応することが困難だというケースも起こり得ます。そういった場合は、会計システムを独自開発するというのも1つの方法です。ここでは、会計システムを独自開発した際のメリットについてご紹介します。
●自社の業務に最適化したシステムを開発できる
会計システムを独自開発することによって、自社の業務フローに最適化したデータの入力や処理を自動化できるようになります。そのため、手作業による入力ミスや計算ミスといったヒューマンエラーを削減し、業務の効率化につながります。また、会計データの分析や情報の抽出がよりスムーズにできるため、経営判断や戦略立案をさらに迅速に行うことも可能になります。月次決算や税務申告などの手続きも自動化できるようになれば、タスク漏れや業務の遅延を防ぐことにもつながります。自社の業務に最適化したシステムを開発することによって、より会計業務を効率化することが可能です。
●セキュリティのレベルを高められる
会計システムを独自開発する際には、企業独自のセキュリティ機能を追加することによって、よりセキュリティのレベルを高めることができます。財務データや個人情報などといった企業の会計情報は、企業にとって重要なデータです。不正アクセスやデータ漏洩を防ぐために、アクセス制御やデータの暗号化といったセキュリティ対策は必要不可欠です。強固なセキュリティ対策を実装し、機密性を確保することは、会計システムの導入において重要な要素の1つです。また、セキュリティレベルの向上は顧客情報の保護にも役立ちます。そのため、企業のブランド力や顧客エンゲージメントの向上にも効果があるといえます。
会計システムの見積もり依頼のコツ
会計システムの見積もり依頼のコツとして、以下の3つが挙げられます。
-
見積もりは複数社にする
-
同じ要望・条件で伝える
-
相見積もりであることも伝える
3つ目の要素は、特に大企業において顕著な傾向にありますが、社内営業するうえでとても重要な要素の1つです。また、複数社の見積もりを確認することによって、各社が提示している内訳が一般的であるかということも、第三者的な視点で評価することが可能になります。
●見積もりは複数社にする
見積もりは複数社に依頼しましょう。とはいえ、たくさんの会社に依頼すると、混乱を招きまとまりにくくなるということも起こり得ます。事前にいくつかの開発会社を候補に挙げておき、その中から2、3社程度にしぼって依頼しましょう。
●同じ要望・条件で伝える
要望や条件は、すべての会社に同じように伝えましょう。各社によって伝えた内容が異なると、相見積もりのメリットでもある費用の比較が困難になります。必ず同じ要望・条件で統一して依頼しましょう。
●相見積もりであることも伝える
複数の会社に相見積もりを依頼していることは伝えることも大切です。依頼している会社名を伝える必要はありませんが、「相見積もりをしている」と伝えることによって、費用面、プラン提案面において、よりよいものが提示される可能性が高くなります。
会計システムの開発における見積もりを確認するポイント
会計システムの開発の見積もりにおいては、依頼だけでなく確認をする際にも大きく3つのポイントがあります。ここでは、各ポイントについて解説します。
-
プロジェクト期間が明確に示されているか
-
開発範囲は明確・妥当かどうか
-
リスクが考慮されているか
●プロジェクト期間が明確に示されているか
システム開発表でプロジェクト期間が明確に示されているか確認しましょう。要件定義からリリースまでの予定が明記され、その期間の人件費が正しく請求されているかチェックするためです。システム開発費用は人件費×作業期間が基準になるため、この期間を明示されていない場合は見積もりの正確性が損なわれます。記載がない場合は質問をし、プロジェクト期間について開発者側の説明を求めましょう。
●開発範囲は明確・妥当かどうか
開発範囲が明確、または妥当かどうかも確認しましょう。見積もりを出す際はシステムの開発範囲と期間を元に人件費を計算するため、開発範囲が曖昧な場合は見積もりの内容が不明確であるといえます。例えば、システムに機能を追加・または改修を依頼する際に、必要のない範囲のシステムが対象になっていないか、作業する範囲をリスト化してもらいましょう。
●リスクが考慮されているか
システム開発の際には、途中でトラブルが起きたり、修正の依頼をしたりすることも起こり得ます。その際に修正に追加費用がかかるのか、または数回の修正が費用に含まれているかもチェックしましょう。また、見積もり計算の前提条件が、自社の要望や状況と一致しているかという点も重要なポイントです。システム要件定義において伝えた要望が叶えられているか、過剰な機能を付加して見積もりを計算していないか確認しましょう。自社でも要望をリストアップしておき、見積もり内容と一緒にチェックをするのがおすすめです。
会計システムの機能と得られるメリット
会計システムに搭載されている機能や、導入をすることによって得られるメリットは様々です。メリットとして、以下の4つが挙げられます。ここでは、会計システムに搭載されている機能や得られるメリットについて詳しくご紹介します。
-
会計業務を効率化できる
-
複数拠点での情報共有を円滑にする
-
経営判断の迅速化に役立つ
-
ペーパーレス化につながる
●会計システムにはこんな機能が搭載されている
会計システムに搭載されている機能は、以下の表のとおりです。
| 帳簿作成機能 | 現金出納帳、総勘定元帳など、伝票の取引状況から転記して帳簿を作成する機能 |
|---|---|
| 決算書作成機能 | 入力したデータをもとに、貸借対照表や損益計算書などの、会計業務に必要な決算書を作成する機能 |
| 振替伝票作成機能 | 取引を振替伝票として作成する機能 |
| 財務管理機能 | 入力データをもとに貸借対照表や会計帳簿などに反映する機能 |
| 各種レポート作成機能 | 会計データを反映してグラフ化や表化されたレポートを作成する機能 |
| 経営分析機能 | 企業の経営状況や財務状況の客観的なデータを抽出し、様々な会計データや帳簿内容を自動分析する機能 |
導入するシステムによって搭載されている機能は異なりますが、上記に挙げた機能は一般的な機能です。
●メリット1:会計業務を効率化できる
会計システムを導入することによって、会計業務の負担を減らし、効率化できる点がメリットとして挙げられます。システムを導入していない場合は、帳簿作成や伝票入力などといった作業で日々の経理業務に多くの時間や手間が必要になります。しかし、システムを導入することによって、仕訳の一括入力や起票の自動化などができるようになります。システムに入力した取引データの自動仕訳機能が搭載されていれば、複式簿記の専門知識を持っていなくても問題ありません。また、企業によっては経理以外の部署の従業員や、経営者が会計業務を兼任していることもあり得ます。そういった場合は、会計システムを導入し会計業務を効率化することによって、よりコア業務に集中することができるようになります。
●メリット2:複数拠点での情報共有を円滑にする
企業によっては、本社と支社のように拠点が分散しているケースもあります。会計システムの導入によって、複数拠点でデータ共有ができるため、情報共有がより円滑になります。複数拠点を持つ企業の場合、会計業務を紙ベースで行っていると、帳簿を確認する作業だけでも拠点間のやり取りに大きな手間と時間が必要になります。会計データは、取引の記録が蓄積されたデータです。そのため、企業の現状を把握したり、経営戦略を立てたりすることに役立ちます。状況に適した経営判断をするためには、複数拠点の会計データを本社や経営陣がスムーズに確認できる仕組みが重要です。会計システムでデータを一元管理しておくことで、離れた場所からでもリアルタイムでのデータの確認が可能になります。
●メリット3:経営判断の迅速化に役立つ
前項でも触れましたが、事業の継続や拡大には状況に応じた経営判断を迅速に行うことが重要な要素の1つです。会計システムの各種レポート作成機能によって、損益や残高、借り入れ残高などといった自社の状況を正確に確認できます。そのため、経営判断の迅速化に役立ちます。業績が悪化する兆候があった際にも、迅速に対応することが可能です。また、会計システムを導入すると、リアルタイムで試算表を作成することが可能になるため、月次決算や四半期決算の際の会計業務の負担が軽減されます。月次決算を早期化することも、迅速な経営判断につながります。
●メリット4:ペーパーレス化につながる
会計システムは、帳票や帳簿、財務諸表などそれぞれのデータをデジタル化して一元管理できます。デジタル化されたデータで運用することができるため、ペーパーレス化につながる点もメリットとして挙げられます。ペーパーレス化することによって、印刷にかかる費用や紙の資料の保管場所、管理にかかるコストを削減することも可能になります。また、ペーパーレス化によって、経理部門の従業員がオフィスに出社しなくても業務が可能になるため、働き方改革にもつながるといえます。
会計システム導入時の手順
会計システムの導入に成功するためには、導入するまでの手順も重要な要素の1つです。会計システムの導入の手順は、以下のとおりです。各手順を解説します。
-
会計システムの導入目的を洗い出して明確にする
-
必要な機能を洗い出す
-
システムの比較・選定を行う
-
導入・運用して効果測定を行う
●会計システムの導入目的を洗い出して明確にする
導入目的を明確にできず、導入すること自体が目的になってしまうと、機能面やコスト面だけでシステムを選定し、定着せずに失敗してしまうということも起こり得ます。まず、自社の現状や課題を洗い出し、「どのような課題を解決したいのか」「解決するためにはどのような機能が必要なのか」を明確にしましょう。また、実際に会計業務に携わっている従業員の間でも、社内での役割や担当業務によって立場が異なることもあります。経営陣、システム担当者、実際に運用する部門の従業員などといった、それぞれの立場からの異なる視点で現状分析を行い、課題と課題解決に必要な機能を洗い出し明確にしましょう。
●必要な機能を洗い出す
会計システムの導入目的や課題を洗い出して明確にすることができたら、課題解決のために必要な機能をリスト化してみましょう。課題解決のために必要な機能としては、以下が考えられます。
-
ほかの業務システムとの連携
-
作業時の入力支援・補助
-
データのインポート・エクスポート
-
会計基準や税法などに対応するコンプライアンス関連機能
-
セキュリティ対策
リストアップする際に、必要な機能がすべて挙げられているかということだけでなく、不要な機能が盛り込まれていないかという点にも注意しましょう。自社の会計業務には必要ない機能が付属していると、操作が煩雑になることから業務効率が下がったり、コストが嵩んだりすることも起こり得ます。システム全体のアルゴリズムや、業務の想定フローチャートを作成するのも効果的です。
●システムの比較・選定を行う
前項でリスト化した機能を備えているサービスをピックアップしていきます。まず、自社の求める条件を満たしているサービスを3~5種類程度選定しましょう。選定したサービスベンダーに情報提供依頼書を提出して、得られた製品情報を比較しながらシステムを絞り込むのがおすすめです。絞り込むことができたら、ベンダーに提案依頼書を提出し、改めて具体的な提案やプレゼンテーションなどを受ける流れになります。無料トライアルがあるサービスの場合は、実際の環境で試し、操作性や使用感を確認するのがおすすめです。
●導入・運用して効果測定を行う
運用を開始する際には、システム利用者全員を対象とした研修会の開催や社内向けのマニュアルを作成しましょう。開発会社にサポートしてもらうことができればなお良いです。会計システムは導入して完了ではなく、継続して運用し定着させることが重要です。導入直後は、従業員が作業に慣れないため、業務量が増加してしまうことも起こり得ます。そのため、会計システムの導入効果を実感するまでには、ある程度の時間が必要です。また、運用後は効果測定をすることも重要です。導入した会計システムによってどのような成果が出たか、新たな課題点はあるかなどを確認しましょう。効果測定の実施により、システム導入の成果が可視化されるだけでなく、より効率の良い運用が可能になります。そのため、より多くの成果が見込めます。
自社に合った会計システムを導入しよう!
会計システム開発の見積もりを確認した際に予算に収まらない場合は、インストール型やクラウド型の導入やASPの利用も検討しましょう。インストール型やクラウド型のシステムは、1から開発する必要がないため、比較的安価に購入できます。ASPはアプリケーション・サービス・プロバイダの略称で、プロバイダにあらかじめインストールされたアプリケーションをレンタルして使う方式です。インストール型は買取方式であり、別途カスタマイズができるため、自社の運用システムに合わせやすいというメリットがあります。その一方で、ASPはレンタル方式であり、費用自体は安価ですが、カスタマイズ性は低く、自社の業務にフィットしない可能性があるため、注意が必要です。
従来は、会計入力をするためには日商簿記2級の知識が必要とされていました。そのため、会計ソフトは会計の知識がある方しか使いこなせないものでした。しかし、現在は、勘定科目の内容と会計入力のルールの理解ができれば、使いこなせる会計ソフトも提供されています。近年は一言で会計システムといっても、様々な種類のシステムが開発・提供されているため、自社に最適な会計システムを検討しましょう。
会計システム導入で開発会社を見つけるには?
発注ナビであれば、全国6000社を超える開発会社のネットワークを駆使し、会計システムの開発・導入支援に対応している開発会社をご紹介いたします。専門知識をもったコンシェルジュが最適な発注先をご提案いたします。平均4~5社を厳選し、最短1日でご紹介!ご相談からご紹介までは完全無料です。「自社に合った開発会社がわからない」「選定にできるだけ時間をかけずにスムーズに導入したい」とお考えのご担当者様はぜひ一度ご検討してみてはいかがでしょうか。発注ナビが選ばれる理由や、導入事例についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。
システム開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国6000社以上からご提案