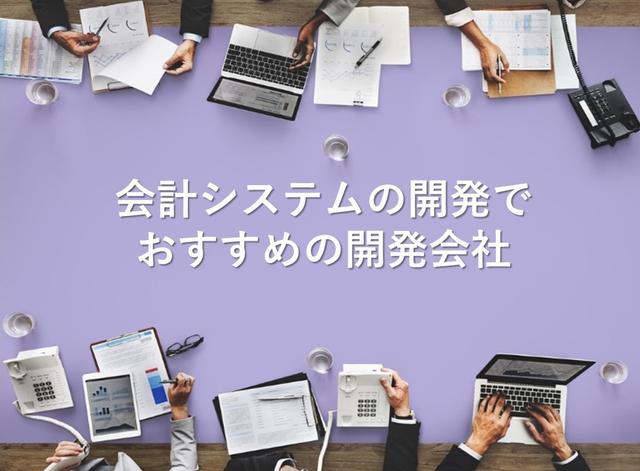基幹システムは、業務の中心となる情報を一元管理するシステムです。基幹業務をデジタル化することで、効率化やヒューマンエラーの削減ができるのが魅力です。ですが、基幹システムならどれでも良いというわけではありません。短納期や安い金額のみに注目してしまうと、自社の業務と合わずにシステムを活かしきれないことがあるためです。
本記事では、基幹システムの基礎から導入時のポイントはもちろん、開発会社の選び方までを紹介します。基幹システム導入時の判断材料として、ぜひ参考にしてください。
目次
システム開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国6000社以上からご提案
基幹システムとは?
基幹システムは、自社業務の核となる情報を管理するシステム(またはソフトウェア)の総称です。よりわかりやすくいえば、基幹システムは「企業がビジネスを遂行するため、業務上必要となるシステム」といえます。
基幹システムは、企業規模や経営状況といった重要な情報管理を行い、企業経営の意思決定を担うバックオフィスにシステムが集中していることが多いため、「バックオフィス系」と呼ばれることもあります。以下では、代表的な基幹システムをいくつか紹介します。
基幹システムが取り扱う業務の種類
企業や業種によって基幹システムの具体的な特徴は異なるものの、大きく以下の5つに分けられ、システムごとに提供できるサービスに違いがあります。
-
生産管理システム
-
販売管理システム
-
購買管理システム
-
在庫管理システム
-
統合基幹業務システム(ERP)
それぞれの基幹システムが持つ特長について解説していきます。
●生産管理システム
生産管理システムは、主に製造業(メーカー)で用いられている基幹システムです。製造業の要となる仕入れ~生産までのプロセスを一元化でき、状況を随時確認できます。具体的には、計画通りに製造・出荷するための進捗管理や、仕入在庫・製造済みの商品在庫・出荷状況などを管理します。
●販売管理システム
販売管理システムは、実店舗やECサイトで広く利用されるシステムです。どの商品が売れているのか、売れた商品の物流はどうか、どの商品が在庫を圧迫しているのか、売上・仕入値はいくらか、料金に対する実際の利益はどれくらい出ているかなど、販売における情報を業務データとして正確に管理して可視化でき、分析に活用できます。
●購買管理システム
購買管理システムは、主に小売業、卸売業、製造業の基幹システムとして利用されています。注文書の作成・出力、支払管理、支払伝票の発行といった購買に関する業務プロセスをシステム化することで問題点の解決やワークフローの最適化に役立ち、生産性を向上できます。
●在庫管理システム
在庫管理システムは、その名のとおり、業務上必要となる在庫をまとめて管理します。完成品を格納する在庫だけではなく、製造用の部品・原材料、製造途中の半製品なども含まれます。管理や情報共有の必要を伴う「在庫」が多岐にわたる小売業・製造業を中心に活用されている基幹システムです。ほかの基幹系システムと連携して使用することが多いのも特徴の一つで、生産管理だけではなく、販売管理や購買管理などと一緒に使われるケースもあります。
●統合基幹業務システム(ERP)
統合基幹業務システムは、生産管理、販売管理など複数部門のシステムをパッケージ化し、管理機能を一元化して最適化させることで、効率的かつスムーズなシステム運用が行えるようにしたものです。企業の規模によってはかかわる業務の範囲も大きくなりやすく、それぞれのデータを別々のシステムで管理・運用することによって、ワークフローが煩雑になることがあります。
そこで、基幹システムを一つにできる統合型の基幹業務システムを導入して、業務全体をまとめて管理するケースも少なくありません。例えば製造業の場合、生産管理・購買管理・在庫管理などのシステムに加えて、会計・人事給与・勤怠管理といった人事・会計に関するシステムが基幹システムとして搭載されています。中でも製造の基幹となる生産管理・購買管理・在庫管理を担うシステムは、同じデータをシェアして利用するため、より詳細な分析が可能です。
これらの基幹業務システムを統合的に管理できるのが、統合基幹業務システムの特徴です。このように基幹となる複数のシステムを充実させ一元化するため、「業務統合パッケージ」とも呼ばれます。
基幹システムの主な機能
基幹システムは、企業の重要な業務を統合的に管理するためのシステムです。基幹システムがあることで、業務に関係する多くの情報を一元管理でき、業務の効率化が図れます。
●生産管理システムの機能
生産管理システムは、企業の製造工程を効率的に管理するのに特化したシステムです。まず、生産計画の立案機能は、需要予測や在庫状況を基に最適な生産スケジュールを作成します。スケジュールにより、過剰生産や欠品を防ぎ、資源を効率的に活用することが可能です。
そして、生産計画の管理機能は、計画どおりに生産が進んでいるかをモニタリングし、必要に応じて調整を行うために使用します。この機能は、計画と実績のギャップを把握し、迅速に対応するために欠かせません。
資材管理機能は、必要な資材の発注や在庫を管理し、欠品や過剰在庫を防ぎます。生産ラインの停止を防ぎ、コストを削減することが目的です。製造管理機能は、品質管理や工程管理を含む製造プロセス全体を管理し、効率的な生産活動を支援することで、製品の品質を保証します。
最後に、原価管理機能は、生産にかかるコストを詳細に把握し、コスト削減のための分析を行い、利益率の向上を目指せます。これらの機能が統合された生産管理システムは、企業の競争力を高めるためには不可欠なツールです。
●販売管理システムの機能
販売管理システムは、企業の販売活動を効率的に管理するシステムです。
見積もり管理機能は、顧客に提出する見積もりを作成・管理し、営業活動を支援してくれます。支援機能により、見積もりの精度向上と迅速な対応が可能になります。顧客からしても、スピーディーな対応は好印象です。
売上管理機能は、商品の売上情報を一元管理し、売上分析や予測を行います。リアルタイムで売上状況を把握できるのが特徴で、経営戦略の立案やマーケティング活動の効果測定に役立ちます。
請求管理機能は、請求書の発行とその後の管理をする機能です。請求書の作成から送付、支払い確認までのプロセスを効率化し、未収金の発生を防ぎます。入金(債権管理)機能は、顧客からの入金状況が管理できるため、未収金があればすぐ把握でき、回収の対応がとれます。これにより、キャッシュフローの改善と資金繰りの安定化が可能です。
さらに、販売管理システムは、顧客情報の管理や販売プロセス全体の最適化を支援し、顧客満足度の向上を目的としています。こうした機能を活用することで、企業は効率的な販売活動を実現し、競争力を高めることが可能です。
●購買管理システムの機能
購買管理システムは、企業の調達業務を効率化するためのシステムです。調達価格の管理機能では、購入する材料や部品の価格を管理でき、コストの最適化が可能です。結果、調達コストの削減と利益率の向上が図れます。
発注管理機能は、発注書の作成、送付、受注確認までの工程の自動化を可能とし、発注プロセス全体を効率的に管理することで、必要な資材を必要な時に調達することが可能です。仕入管理機能は、物品の仕入作業を効率的に管理します。結果、仕入れた物品の品質管理と在庫の最適化ができます。
納期管理機能は、発注した物品の納期や適切なタイミングでの受け取りを管理することで、納期遅延の防止、生産スケジュールの調整を容易化することが可能です。支払い(債務)管理機能は、仕入先への支払いを管理してキャッシュフローを最適化するために、支払いのタイミングを調整して、資金繰りを安定させるのに役立ちます。
購買管理システムは、調達業務全体の透明性を高め、サプライチェーン全体の効率化を支援してくれるシステムです。これらの機能を活用することで、企業は調達コストを削減し、競争力を高めることができます。
●在庫管理システムの機能
在庫管理システムは、企業の在庫を効率的に管理するためのシステムです。在庫一覧機能は、現在の在庫状況を一覧で確認できるため、在庫の過不足を防ぎ、在庫の最適化が図れます。欠品や過剰在庫は、販売機会を失うことになるため、適正在庫の維持は大切です。
入出荷管理機能は、商品の入庫と出庫を管理し、在庫を正確に把握できる機能です。この機能は、入庫と出庫をリアルタイムで記録してくれます。返品機能は、返品された商品の処理を行い在庫数を管理する機能で、返品処理を効率化します。
棚卸機能は、定期的に在庫を実地で確認し、帳簿上の在庫と照合する機能です。在庫の正確性を確かめ、不足や過剰在庫を早期に発見するのに役立ちます。在庫分析機能は、在庫データを分析し、在庫回転率や滞留在庫がないかを確かめられます。
在庫管理システムは、企業の在庫コストを削減し、顧客サービスの向上を支援してくれます。これらの機能を活用することで、企業は効率的な在庫管理を実現し、競争力を高められます。
●統合基幹業務システム(ERP)の機能
統合基幹業務システム(ERP)は、企業の主要な業務プロセスを統合的に管理するためのシステムです。まず、財務管理機能は、企業の財務状況を管理し、財務諸表の作成や予算管理を行います。この機能により、企業の経営状況を正確に把握し、適切な経営判断を支援します。
会計管理機能は、取引の記録と報告を記録することで、正確な会計情報が得られます。この機能は、会計基準に準拠した報告を手助けしてくれるため、監査や税務申告に役立ちます。人事管理機能は、従業員の情報を管理し、給与計算や労務管理が行えます。従業員の採用、評価、研修、福利厚生など、人事業務全般を効率化してくれる機能です。
さらに、ERPシステムは、各業務プロセスを統合的に管理し、情報の一元化を実現します。業務間のデータ連携がスムーズに行えるため、業務の効率化と情報の可視化が図れます。ERPシステムは、企業の競争力を強化し、持続的な成長を支援するための重要なツールです。
基幹システムを導入するメリット・デメリット
| 基幹システムを導入するメリットとデメリット | |
|---|---|
| メリット | 業務の効率化を実現しやすくなる |
| 業務の属人化を防ぎやすくなる | |
| 業務の自動化によりヒューマンエラーが発生しにくくなる | |
| 情報を一元化してデータの紛失や破損を防ぎやすくなる | |
| デメリット | システムが止まると業務がストップしてしまう |
| 業務にあったシステムでないと効果が半減しやすくなる | |
企業による基幹システムの具体的な導入メリットは、業界やどの職種なのかによっても異なりますが、企業を問わず当てはまる普遍的なメリットも存在します。一方、多くのメリットをもたらす基幹システムが持つデメリットについても把握しておくことが必要です。下記では、基幹システムの主なメリットを4つ、主なデメリットを2つ紹介します。
●基幹システムを導入するメリット
まずは基幹システムの導入メリットについて解説していきます。
業務の効率化を実現しやすい
システムの導入により、これまで手動で行っていた業務プロセスを自動で行えるようになります。仕入・売上管理、見積・請求書管理、CRM(顧客管理)などは、会社の規模が大きくなるほど管理や運用に手間とコストがかかるものです。
しかし、基幹システムがあれば、事前にExcelなどを使ってPCへ情報を入力しておくだけで自動的に数値を更新できるようになるため、作業の大幅な効率化が可能です。また、データ連携が可能な点も業務効率化に大きく貢献します。財務会計では仕入台帳からさまざまな書類を作成する必要があります。システム導入により、仕入データをもとに総勘定元帳や決算書、売掛帳、買掛帳といった必要書類が全て自動的に作成されます。手動で作成する必要がないため、会議に使う資料を準備する時間を短縮できます。
業務の属人化を防ぎやすい
基幹システムによって標準化された業務が社内の共通認識になるため、誰でも一定レベルの業務品質を保てるようになります。これにより、「その作業に特化した特定の人材がいないと業務を遂行できない」といった属人化を防ぐことができます。中堅社員でも新入のアルバイトでも、誰が担当しても同じように業務可能であるため、クオリティの標準化が可能です。
また、業務内容によってはRPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)を絡めてさらに作業の効率化を進めながら、小売店などが基幹システムの機能をPOSシステムに搭載させて、さらに利便性を向上させたりするケースもあります。ほかのシステムやサービスなどと連携させることで、属人化の防止とクオリティの標準化の両方が可能です。
ヒューマンエラーの削減につながる
システムによって業務を自動化できるため、手を動かす作業で起こりがちなヒューマンエラーやミスの削減ができるメリットがあります。システムの手動オペレーションやデータ入力といった作業は、細心の注意を払い、繰り返し確認を行ったとしても、少なからずヒューマンエラーが発生します。基幹システムの導入によって、入力の抜け漏れや計算ミスなどを防げるだけではなく、担当者同士のコミュニケーションロスも防止できるため、小さなミスが大きなトラブルへと発展することを未然に防ぎます。
情報を一元化できる
業務に必要な情報を一元化することで、欲しい時に必要な情報をすぐに抽出可能です。一元管理することで企業規模や経営資源といった企業経営に必要なデータも可視化できるため、最新の経営状況の分析や課題の把握、組織の意思決定などが迅速になるでしょう。また、データの紛失や破損、最新版の重複といったミスにつながりやすい事態が生じる可能性が低くなったり、BI(Business Intelligence)ツールなどで蓄積データと経営指標と照らし合わせ、リアルタイムでの分析や可視化がしやすくなるメリットもあります。
一連の業務で共用される情報は、システムを横断して反映されます。例えば、基幹システムに顧客の基本情報を入れておくと、見積もりや生産、受注、販売を担うシステムに反映され、受注金額は会計システムにも反映されます。情報の一元化により、同データを入力しなおす手間がありません。また、何らかのミスや不具合が発生した時に、どのプロセスに問題があったのか把握することも容易になるでしょう。
●基幹システムを導入するデメリット
導入することでさまざまなメリットを得られる基幹システムですが、導入前に注意すべきデメリットもあります。ここでは、基幹システムを導入するデメリットの代表的なものを2つご紹介します。
システムがダウンすると業務も止まってしまう
「企業の重要業務を管理するシステム」という都合上、一度稼働した基幹システムは基本的に止められません。もし、基幹システムに予期せぬ障害が発生し、システム自体が停止してしまうと、業務に大きな支障を及ぼしてしまいます。
例えば、工場で生産管理システムが停止すれば、生産状況や計画の進捗度が不明確となり、工場全体を一時的に停止せざるを得ない状況に追い込まれる可能性もあります。このように、基幹システムは企業活動のまさしく「基盤」を成しているため簡単に止めることが許されないシステムであり、動作の安定性や高いセキュリティが求められます。
導入効果が得られないおそれがある
仕事の根幹を担う基幹システムといっても、業務に関係のないシステムを導入しても見合った効果を得られません。また、どんなに多機能な基幹システムでも、従業員が使いこなせなければ恩恵も少なくなるでしょう。
そのため、基幹システムを導入する際は「なぜ基幹システムの導入を推進するのか」の導入目的を明確化したり、「どうやって従業員に周知するのか」の内部統制を整えたりする必要があります。さらに、従来のワークフローを見直し、得意分野や強みが異なるさまざまな人材が適切に業務を遂行するための社内教育まで行うのが理想的です。システムを導入するだけですぐに組織内の業務レベルが引き上がるものではないため、基幹システムの導入に伴う働き方の変化も必要になるでしょう。
基幹システムとほかのシステムの違い
企業活動を支えるシステムは、主に「基幹システム」、「ERPシステム」、「情報系システム」、「業務システム」の4つに分けられます。
| 基幹システム | 「企業の核となる業務」の効率化を目指すシステム |
|---|---|
| ERPシステム | ERP(企業が持つ資源を管理・活用する概念)を実現するための統合基幹業務システム |
| 情報系システム | 社内のコミュニケーションや業務効率化を目的に導入されるシステム |
| 業務システム | 業務を行う際に使用するシステムの総称 |
以下ではそれらの概要と、基幹システムとの相違点について解説します。
●基幹システムとERP・ERPシステムの違い
ERPとは「企業資源計画(Enterprise Resource Planning)」の頭文字から作られた言葉を指します。端的にいえば、企業が保有しているヒト・モノ・カネという資源を一元管理して、経営戦略に役立てるという計画(または概念)のことをいいます。
この計画・概念を実現するために作られた業務システムを「統合基幹業務システム」、別名「ERPシステム」と呼びます。
-
ERPは、「企業の資源を一元管理する計画や概念」
-
ERPシステムは、「ERPの概念を実現するためのシステム」
-
基幹システムは、「企業の核となる業務の効率化を目指すシステム」
それぞれの意味を端的にまとめると、上記のような違いがあります。ERPが2つの意味を含有しているため混同されることもしばしばですが、ERPとERPシステムは本来、それぞれ別の意味を表す言葉です。とはいえ、令和の現代ではERPが概念という意味で使用されるケースは少なく、単純にERPというと「システムそのもの」を指すことがほとんどです。
●基幹システムと情報系システムの違い
情報系システムは、メールソフトやオフィスソフト、グループウェア、社内SNSなどが該当します。端的にいえば、社内のコミュニケーションや業務効率化、経費削減の目的で導入されているのが「情報系システム」です。企業の業務遂行に直接は影響せず、トラブルが生じても致命的なダメージを与えないものを指します。
-
情報系システムは、システムがストップしても業務を継続できる
-
基幹システムは、システムがストップすると業務を継続できない
情報系システムと基幹システムとの大きな違いを挙げれば、上記のような相違点があります。例えば、社内SNSが予期せぬ障害によって停止してしまっても、緊急の要件は電話やメールでの代替が可能です。効率性の低下は考えられますが、情報系システムのトラブルによって業務が遂行不可能になるケースはほとんどありません。一方、重要な業務データを管理する基幹システムが止まってしまうと業務全体が遂行不可能となり、大きな支障が出てしまうのです。
●基幹システムと業務システムの違い
企業の核となる重要データを管理するシステムである基幹システムに対して、業務システムとはその企業で業務を遂行するためのシステムの総称を指します。そのため、業務システムのほうが基幹システムよりも種類が多いのが特徴です。
導入している業務システム内に基幹システムの機能を包括しているケースもあるため、企業によっては基幹システムと業務システムは同一のものと認識されることも少なくありません。
基幹システムと業務システムのどちらを導入すべきかわからない場合は、解決したい課題や問題点を洗い出し、どのような機能を持つシステムを導入すべきかを検討したうえで、適切な方を選ぶのがポイントです。
基幹システムの導入形態の主な種類
基幹システムには主にオンプレミス型とクラウド型の2種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。2つの種類のそれぞれの特徴を把握したうえで、自社に最適な基幹システムを導入するのがおすすめです。
●オンプレミス型
オンプレミス型は、自社で用意したサーバにシステムをインストールして使用するタイプの基幹システムです。カスタマイズ性が高いため、自社の業務に合わせて独自に改良を加えやすい点があります。また、強固なセキュリティ環境を構築しやすいため、業務の主軸となる基幹システムと相性が良いのがメリットです。
一方、サーバを用意する必要がある分クラウド型よりも初期費用がかかりやすく、せっかく用意したサーバも機器の老朽化に合わせて数年でリプレース(取り換え)が必要になるのが一般的であり、初期費用以外に月額費用がかかる場合も考慮すると全体的に費用がかかりがちです。
また、テレワークを導入している企業の場合、万が一基幹システムがダウンした際や不具合が起きた場合に、どのように対処するかを社内で確認しておくことが大切です。オンプレミス型の場合はサーバそのものが会社にあるため、テレワーク環境でトラブルが発生した際、クラウド型と比べると正確な状況確認がしづらい傾向がある点や、担当者に出社の必要が出てほかの業務の進捗が滞ってしまう点などへの対策が必要になるでしょう。
●クラウド型
インターネット経由で利用できるクラウド型の基幹システムもあります。近年はクラウドによるDX化の普及が目覚ましく、従来であれば自社でサーバを用意する必要があった基幹システムでもクラウド化が進んでいます。そのため、近年では中小企業向けのクラウド基幹システムをもってソリューションを展開する開発会社も少なくありません。
その理由は、技術の進歩によってクラウドのセキュリティが向上し、重要情報のクラウド化が現実的になったためです。加えて、オンプレミス型の基幹システムの老朽化によって業務に影響が出る企業が相次ぎ、SaaSなどを利用してそれらの問題点をクリアできる新しいシステムのニーズが高まった背景もあります。
基幹システムだけに限らずクラウド化はランニングコストが生じるものの、必要な容量・機能に合わせてサイジングできる柔軟性を持っており、利用目的によってはコストを最小限に抑えられるメリットがあります。また、サーバの追加やCPU・メモリ・ディスク容量の増強といったカスタマイズをシステム停止させずに対応できるため、基幹システムにとっては申し分ない利便性を備えているといえます。
-
社外からも基幹システムを利用したい!
-
常にセキュリティを最新のものに保ちたい!
-
災害に強いシステムを導入したい!
上記のような点を重視したい企業担当者の方であれば、基幹システムをクラウドに移行するのも良い方法です。IT業界におけるクラウドについては、以下のページでも詳しく紹介しているので、ご参照ください。
▷IT業界で使われる「クラウド」とはどういう意味?どんなことができるの?
基幹システムを選ぶ際のポイント
基幹システムの概要を把握できたところで、実際に基幹システムを導入したい企業担当者の方に向けて、基幹システムの選び方について解説しましょう。
●完成度の高いシステムを選ぶ
基幹システムは簡単に停止できないので、利用を開始してしまうとシステムの改修・追加といった気軽な修正が難しいです。また、実際にそのような修正が行われる導入事例はほとんどありません。導入したシステムは長期間使用されるため、初めから完成度の高いシステムの導入が求められます。
本格的な実装前のカスタマイズは可能なため、導入後にトラブルなく好ましい状況でスタートするためには、発注側と開発側双方を絡めた事前の要件定義が大切です。システムの導入目的や解決したい課題を明確にしておきましょう。
●セキュリティが強固なシステムを選ぶ
導入する基幹システムは、一部の経営陣のみでなく企業全体で利用するシステムです。重要な業務に直接関係する情報を管理・処理しており、企業のノウハウが詰まっている「核」となるシステムであることから、機密情報の漏洩やなりすましは許されません。
基幹システムの情報が漏れてしまえば、企業の信頼は失墜するでしょう。令和の現代では、報道やニュースを通じて、銀行や大企業の情報漏洩が大々的に報じられることも珍しくありません。そのため、基幹システムを選ぶ際は、ウイルス対策やパスワード管理、権限設定、変更履歴管理といったセキュリティ対策のための機能が搭載されているかを最低限確認するようにしましょう。
●操作が簡単で覚えやすいシステムを選ぶ
基幹システムは社員だけでなく、アルバイトや派遣社員、発注担当者など社内外を問わず多くのユーザーが操作します。そのため、コマンド形式の操作や複雑なインターフェースだと、「難しくて使いこなせない」というユーザーも出てきます。基幹システムは誰が見ても直感的で操作しやすく、簡単に覚えられるシステムであることが大切です。
とはいえ、取り扱う事業や商習慣、業務内容などによっては、既存の基幹システムをある程度カスタマイズするだけでは「業務に見合った最適な基幹システムとわかりやすいインターフェースを両立できない」というケースもしばしばです。そのため、企業によっては、自社の業務に最適なシステムを導入すべく「基幹システムをゼロから開発する」というケースもあります。
●システムの導入形態で選ぶ
先述したとおり、基幹システムにはオンプレミス型とクラウド型の2種類の導入形態があります。導入する基幹システムを選ぶ際は、自社の環境や働き方、提供するサービスなどをさまざまな面から分析し、より適している導入形態のシステムを選ぶのがおすすめです。
また、基幹システムの導入に伴い、当初のものとは別の課題が浮かび上がった場合、導入形態を変えることでその課題も一緒に解決できるケースもあるでしょう。例えば、「オンプレミス型の基幹システム開発を外部ベンダーに依存していて、自社内に直接的なノウハウを持っていないために、基幹システムの再構築にメリットを感じられない」という背景を持つ会社の場合は、深いノウハウを持たないユーザーでも使いやすい仕様のクラウド型基幹システムを導入することで、外部ベンダーへの属人化・依存化の課題をクリアできるでしょう。
●自社に合った機能の有無で選ぶ
基幹システムを選ぶ際は、自社に必要な機能が搭載されているかどうかをチェックするのはもちろん、既存の社内システムと連携可能かどうか、干渉の有無や相性はどうかなどを事前に確認しておきましょう。基幹システムはほかの業務システムと連携させたり、一つのシステムに機能を集約させることが多いため、導入することで少なからず既存のシステムへも変化が起こるでしょう。
例えば、生産管理や在庫管理といった代表的な機能のほかに、人事給与システムや顧客管理システムの機能を基幹システムにまとめることが可能な場合、現在使用しているシステムの使用を取り止めるのか、などは事前に検討が必要でしょう。
●サポート体制の充実度で選ぶ
基幹システムには万全の体制やセキュリティ強化が必須とはいえ、システム運用上の不意なトラブル対応はつきものです。そのため、重要な機密情報を多く取り扱うため、万が一の事態に備えたサポート体制が充実しているシステムを選ぶことをおすすめします。
なおこの時、システムの欠陥やヒューマンエラーによる障害以外に、地震や火災といった自然災害によって障害が起こる可能性も想定して対策を講じるのが望ましいでしょう。自社内のサーバではなくクラウドサービスのデータセンターを介して使用するクラウド型の基幹システムであれば、社内で事故や災害が起きた場合などの緊急時でもデータ破損などの心配が少ないだけでなく、原状回復や事業継続がしやすいためBCP(Business Continuity Plan)対策にもなるメリットがあります。
基幹システムの開発会社はどう選ぶ?
基幹システムの開発会社を選ぶ際には、開発実績、運用保守の対応、強みや得意分野、担当者との相性など、いくつかの重要なポイントがあります。これらの要素を総合的に判断することで、ニーズに見合った最適な開発パートナーを見つけることができます。
●開発実績は十分か
基幹システムの開発会社を選ぶ際、まず確認すべきはその会社の開発実績です。開発実績を確認するには、会社の公式Webサイトや過去のプロジェクトの事例紹介を参考にすると良いでしょう。また、ほかの企業の口コミや評判を確認することも、実績を把握するうえで有効です。
特に、自社が導入を考えているシステムと類似したプロジェクトの実績があるかどうかを確認しましょう。多くの開発会社は、ベースとなるパッケージを持っており、それをもとにカスタマイズして開発を進めることが一般的です。類似の開発実績がある場合、既存の知識や技術を活用したスムーズな開発が期待できます。さらに、実績のある会社は過去のプロジェクトで得たノウハウがあるため、問題解決や提案力が高い傾向にあるのも特徴です。
●運用保守の対応があるか
システム開発は、システムがリリースされた後も運用保守が必要です。システムが稼働し始めた後に発覚するバグの修正や機能追加、システムの最適化などが求められるため、リリース後の運用保守をワンストップで対応してくれる開発会社であればスムーズです。
事前に運用保守の体制や対応内容を詳細に確認し、納得のいくサポートを提供してくれるかどうかを判断しましょう。運用保守の内容には、定期的なシステムの点検や更新、緊急対応の体制などが含まれます。これらのサービスがしっかりと提供されることで、システムの信頼性と長期的な運用が保証されます。
●強みや得意分野が明確か
開発会社にはそれぞれ得意とする分野や技術があります。例えば、特定の業界に特化したシステム開発や特定のプログラミング言語・フレームワークに強みを持つ場合があります。自社のニーズに合った強みを持つ開発会社を選ぶことで、より高品質なシステムの開発が期待できるでしょう。
事前に開発会社の強みや専門分野を確認することで、自社のプロジェクトにマッチした会社と出会う可能性が高まります。開発会社の得意とする技術領域を把握するためには、以下の方法が有効です。
- 会社の公式Webサイト:提供するサービスや技術に関する情報を確認する。
- 技術ブログ:最新の技術動向や実績に関する記事を読む。
- 公開されている技術資料:具体的な事例や技術的な成功例を確認する。
これらの情報を活用することで、開発会社の専門性と技術力をより具体的に理解できます。
●担当者との相性は良いか
システム開発は短くても数ヶ月、長ければ1年以上かかるプロジェクトのため、担当者との相性は非常に重要です。プロジェクトを進めるにあたってコミュニケーションを頻繫に交わすため、信頼できる担当者との連携が不可欠です。
複数の開発会社に相談し、担当者と直接やり取りをすることで、コミュニケーションの取りやすさや相性を確認できます。実際にミーティングや打ち合わせを行い、コミュニケーションスタイルや問題解決のアプローチを評価しましょう。また、担当者が過去にどのようなプロジェクトを担当してきたかを確認して、その経験やスキルを把握することも有効です。
信頼できる担当者と連携を取り合うことで進行がスムーズになり、予期せぬ問題にも迅速に対応してもらえます。良好な関係を築ける担当者と協力することで、プロジェクトの成功に近づけるでしょう。
基幹システムの開発・導入を依頼できる開発会社
発注ナビ内で掲載および紹介されている企業をいくつかピックアップし、それぞれの対応領域や対応エリア、システム開発の実績について紹介します。
●インフォニック株式会社
インフォニック株式会社は、2020年に設立されたシステム開発会社で、基幹系システムのセミオーダー開発を得意としている会社です。Salesforceプラットフォームでのアプリ開発やセンサーデータのトラッキングシステムなどの開発実績があります。既存のシステムに機能を追加する形でのセミオーダー開発により、コストを抑えながらも顧客の要望に応えたシステムを開発してくれます。
| 所在地 | 東京都中央区銀座7-14-16 太陽銀座ビル4F(東京本社) |
|---|---|
| 設立 | 2020年12月 |
| 対応エリア | 全国 |
| 対応領域 | 業務システム、Webシステム、サーバ・クラウド |
●株式会社システムエグゼ
株式会社システムエグゼは、1998年に設立され、損保・生保向けの業務システム開発を中心に、メーカーの生産管理や会計、医療分野にも対応しています。幅広い業種でのシステム開発の実績があり、クラウド活用やコストメリットを考慮した開発が得意です。システム導入後の保守も含めたトータルサポートを提供します。
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F |
|---|---|
| 設立 | 1998年2月 |
| 対応エリア | 関東、中部・北陸、関西 |
| 対応領域 | 業務システム、Webシステム、サーバ・クラウド |
●株式会社シスディブリンク
株式会社シスディブリンクは、多くの企業向けに基幹システムの開発と導入を行っている会社です。寄合型生産管理システムをWebパッケージシステムとして提供しています。顧客の業務効率化を実現するために、カスタマイズされたソリューションを提案し、業務の流れを改善してくれます。また、導入後の運用サポートも充実しており、長期的なシステムの安定稼働を支援します。
| 所在地 | 愛媛県西条市大町453-7 |
|---|---|
| 設立 | 2015年 |
| 対応エリア | 全国 |
| 対応領域 | 寄合型生産管理システム |
●株式会社ライフエッグ
株式会社ライフエッグは、神奈川県海老名市に拠点を置く企業で、2014年の設立以来、ガジェットメーカー事業、プリント事業、ワイン事業など多岐にわたる事業を展開してきました。これまでに多くのプロジェクトを成功させてきた背景には、優れた企画力と実行力があります。お客様との密なコミュニケーションを通じてプランを立案し、デザイン検討や仕様書作成など、製品が届けられるまで徹底的にサポートしています。また、グループ会社のシステム構築で培ったノウハウを活かし、自社に合うシステムやWebサイト構築を提案してくれます。
| 所在地 | 神奈川県海老名市中新田5-24-1 |
|---|---|
| 設立 | 2014年2月14日 |
| 対応エリア | 全国 |
| 対応領域 | 販売管理システム、在庫管理システム、顧客管理システム |
基幹システムを導入する流れ
基幹システムを導入する際は、以下の流れに従って適切な手順で進めるのがおすすめです。
-
企画
-
要件定義
-
実装
-
運用・保守
●STEP1:企画
いきなりシステム開発を外注先へ依頼するのではなく、はじめに基幹システムを導入することで解決したい経営課題や、改善したい経営指標を明らかにしましょう。基幹システムの導入によって日々の業務効率を上げ、導入効果を最大化させるためには、自社が抱える経営課題を抽出し、社内業務のどのようなポイントにシステム導入が必要なのかを企画の段階で明確にしておくことが重要です。
本格的に開発を発注する前に、まずは経営課題の解決や経営指標の改善のために必要なものは何かを理解するための分析を重ね、それらを改善できる基幹システムを選定してみましょう。
また、基幹システムは会社の中枢部分を担う重要なデータが集まるものであり、業務遂行のために経営陣から現場スタッフ・外部パートナーまで幅広いユーザーが利用するシステムです。企画と並行して複数の部署を横断するプロジェクト体制を整えておくと、システムの運用に伴う社内への周知や運用のための教育といったさまざまな情報共有がスムーズになります。
●STEP2:要件定義
改善すべき経営課題や経営指標が明らかになったら、それらを踏まえて具体的にどの業務をシステムで改善すべきかを洗い出す要件定義を行い、RFPなどにドキュメント化したうえで開発側へ共有しましょう。
この要件定義も企画と同様、社内で十分な時間を取って行う必要がある作業です。特に、基幹システムは実装後の仕様変更が難しいため、開発や実装に着手する前に必要な機能と不要な機能を明確にしておくことが不可欠です。長期的視点と導入や運用のコストも視野に入れつつ、丁寧に検討を進めましょう。
また、基幹システムの導入効果を上げるためには、システム導入のみで全てを改善しようとするのではなく、業務プロセスに無駄がなくなるよう制度や仕組みを修正したりといった社内調整も並行して行うのがポイントです。
●STEP3:実装
具体的な要件定義を基にしたシステム開発が進んだら、完成目前の段階でテストを行います。不具合が出ないか、誰にでも扱いやすいインターフェースになっているか、新たな機能の追加や不要な機能の削除は必要ないかなどをチェックし、必要に応じて再テストや総合的な品質確認を行います。
テスト完了後特に問題がなければ、いよいよ本格的に基幹システム実装となります。リリースまでの間に、ここまでに計画しておいた社内への情報共有や教育を進めておくと、運用開始以降の流れがさらに効率的になるでしょう。
●STEP4:運用・保守
システムは納品されて終わりではありません。自社内や現場などのさまざまな環境で実際に運用を行いながら、システム導入後にどの程度の改善効果が出ているのか測定することが大切です。企画で挙がった課題がシステムの導入で改善されたかを確認し、改善がみられなかった場合は今後何が必要なのかを再度検討することも必要でしょう。
ただし、システムを導入したばかりの初期段階では、運用に慣れていないために効果的な使い方ができないこともあるでしょう。システムそのものを見直すべきか、システムを運用するための仕組みを見直すべきかどちらなのかは慎重な判断が必要です。
また、運用開始後になってシステムの不具合や問い合わせたい相談事が見つかることも少なくありません。そのため、システム実装後も開発側との連携を取っておくのがおすすめです。効果測定の情報共有も兼ねながら、運用・保守に関するノウハウの共有やアドバイスをもらうのも良いでしょう。
基幹システム導入までに必要な時間
基幹システムの導入期間は、システムの種類や規模によって異なります。計画を立てる際には、カスタマイズの有無や運用体制、組織の規模などを考慮することが重要です。
●オンプレミス型システムの場合
オンプレミス型システムの導入には、カスタマイズの有無やプロジェクトの複雑さによって期間が大きく変わります。カスタマイズを行う場合、まず要件定義を徹底的に行う必要があります。ここで必要な機能や性能、予算、スケジュールを明確にします。その後、設計フェーズに移り、システムの詳細な設計図を作成します。この段階では、ハードウェアやソフトウェアの選定も行います。
設計が完了すると、実際の開発に進みます。開発では、プログラムの作成と同時に、システムのテストも並行して行います。このテストには、単体テスト、結合テスト、システムテスト、受け入れテストが含まれます。各テストは、システムの各部分が正しく動作することを確認するために重要です。これら全てのプロセスを経ると、導入までに最低でも6ヶ月以上かかることが一般的です。
一方、ノンカスタマイズの場合、標準機能を利用するため、要件定義や設計のフェーズが簡略化され、開発期間も短縮されます。この場合、約3ヶ月ほどで導入が完了します。しかし、どちらの場合も、導入後の運用保守や社員教育の時間も考慮しなくてはいけません。特に新しいシステムに慣れるためのトレーニング期間は、スムーズな運用開始のために不可欠です。
●クラウド型システムの場合
クラウド型システムの導入は、オンプレミス型に比べて迅速に行えるのが特徴です。クラウド型システムは、初期設定が比較的簡単で、インフラ構築の手間がかからないため、短期間での導入が可能です。
一般的には、カスタマイズの度合いにより数ヶ月から1年以内で導入および運用が完了します。まず、クラウドサービスプロバイダーとの契約を結び、必要なサービスを選定します。この段階では、必要なリソースの見積もりや、セキュリティ対策の確認が行われます。その後、システムの設定を行い、データの移行を実施します。
クラウド型システムのもう一つのメリットは、柔軟なスケーラビリティ(拡張性)です。必要に応じてリソースを増減できるため、企業の成長や変化に応じたコスト管理が行いやすいでしょう。また、クラウドサービスは新しい技術やセキュリティアップデートが開発側から提供されるため、システムの維持管理が容易です。これにより、企業は本業に集中できる環境が整います。
さらに、クラウド型はリモートワークの推進にも役立ちます。どこからでもアクセス可能なシステムは、従業員の働き方を柔軟にし、業務効率を向上させます。これらの利点から、現代では多くの企業がクラウド型システムを選択しています。
●小規模な組織で導入する場合
小規模な組織で基幹システムを導入する場合、システムの複雑さや導入範囲によって期間が異なりますが、一般的には数ヶ月から1年未満で完了します。小規模な組織では、迅速な導入が求められるため、クラウド型システムが選ばれることが多いためです。
クラウド型を利用することで、初期コストを抑えつつ短期間でシステムを稼働させることが可能です。まず、導入するシステムの選定が重要です。小規模な組織では、シンプルで操作が容易なシステムが求められます。選定後、システムの設定とデータ移行を行います。データ移行は、既存データのバックアップを取り、新システムに適した形式で移行することを含みます。
次に、社員への教育が必要です。新しいシステムを効果的に使用するためには、社員がシステムの機能や操作方法を理解していることが重要です。トレーニングセッションを開催し、実際の操作を通じてシステムに慣れてもらいます。
クラウド型システムは、柔軟な料金体系が多く、使用した分だけ支払う従量課金制や月額料金制などが一般的です。これにより、小規模な組織でも予算を管理しやすくなります。また、クラウドプロバイダーによっては、24時間365日のサポートを提供しているため、問題が発生した際も迅速に対応してもらえます。
●大規模な組織で導入する場合
大規模な組織で基幹システムを導入する場合、導入期間は1年単位で計画するのが一般的です。大規模な組織では、データ移行のボリュームやセキュリティ要件の厳格化など、多くの要素を考慮する必要があります。
プロジェクトの初期段階では、詳細な要件定義を行います。この段階で、組織全体のニーズや要望を把握し、具体的なシステムの仕様を決定します。要件定義が完了すると、設計フェーズに進みます。設計では、システムのアーキテクチャやデータベースの構造を詳細に設計し、全体のシステム設計図を作成します。
設計が完了したら、次は実際の開発段階です。開発では、多くの開発者が協力してシステムを構築し、複数のテストフェーズを経て品質を確認します。単体テストや結合テスト、システムテスト、ユーザー受け入れテストを実施し、各部分が正しく動作することを確認します。大規模システムでは、特にテストの重要性が高く、十分な時間をかけることが求められます。万が一にでも不具合があった場合の影響が大きいためです。
また、大規模な組織では、複数の部門や拠点にシステムを導入しなくてはいけません。このため、段階的な導入が一般的です。各部門や拠点ごとに導入計画を立て、順次システムを展開していきます。この際、各部門の特性や業務プロセスに応じたカスタマイズが必要となるケースもあります。
さらに、システム導入後の運用保守や社員教育も重要な要素です。前述したように、トレーニング期間を設けましょう。そして、大規模な組織では、システムの安定運用が業務効率に直結するため、運用保守の体制をしっかりと整えることも必須です。
基幹システムの導入で、業務効率の大幅な改善を図る
基幹システムの導入や開発、リプレースは大仕事です。システム導入には多くの時間とコストがかかりますが、適切なシステムを導入することで業務効率を大幅に改善できます。そのため、システム導入の初期段階から信頼できるベンダーを選び、サポートを受けることが重要です。
もちろん導入の初期コストは発生しますが、品質に優れ、業務プロセスに沿った基幹システムを導入できれば、自動化によるコスト削減や属人化の防止、ヒューマンエラーの削減など企業全体の業務効率を大幅に改善できます。導入する際は現状の業務プロセスと比較し、自社に最適なシステムかどうかをしっかりと見極めて、ビジネスに役立てましょう。
また、本格的な開発と導入に入る前に、要件定義やRFPの提出をはじめとした開発会社への積極的な情報共有が重要です。導入後の機能追加や修正が難しいことから、わからない点や不明点はぜひ開発会社へお問い合わせください。
発注ナビであれば、全国6000社以上の開発会社の中から、ご要望や案件内容に合った開発会社を厳選してご紹介いたします。『自社に合った開発会社がわからない』『選定にできるだけ時間をかけずにスムーズに導入したい』とお考えのご担当者様はぜひ一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
システム開発の最適な発注先をスムーズに見つける方法
システム開発会社選びでお困りではありませんか?
日本最大級のシステム開発会社ポータルサイト「発注ナビ」は、実績豊富なエキスパートが貴社に寄り添った最適な開発会社選びを徹底的にサポートいたします。
ご紹介実績:25,000件、登録社数:7,000社(2025年5月現在)
外注先探しはビジネスの今後を左右する重要な任務です。しかし、
「なにを基準に探せば良いのか分からない…。」
「自社にあった外注先ってどこだろう…?」
「費用感が不安…。」
などなど、疑問や悩みが尽きない事が多いです。
発注ナビは、貴社の悩みに寄り添い、最適な外注探し選びのベストパートナーです。
本記事に掲載するシステム会社以外にも、最適な開発会社がご紹介可能です!
ご相談からご紹介までは完全無料。
まずはお気軽に、ご相談ください。 →詳しくはこちら
システム開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国6000社以上からご提案