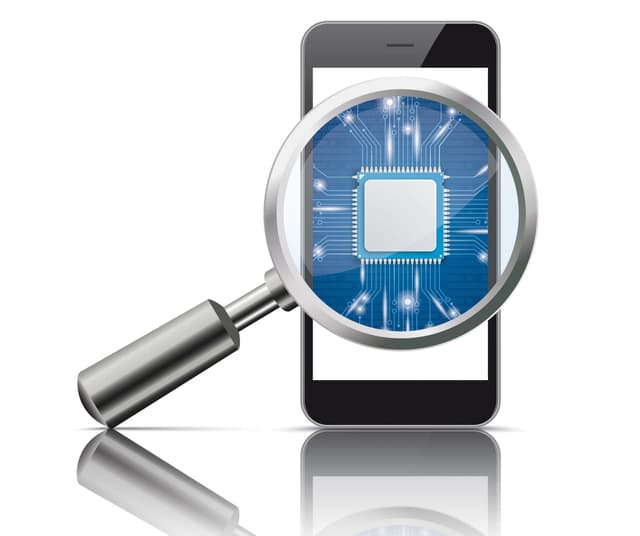既存システムの改修とは、現状よりも使いやすくすることを目的とした作業です。「消費税が変わったので、社内の精算機能システムを改修したい」などの要望が出ることもあるでしょう。
ここではシステム改修について詳しく解説したうえで注意点もお伝えしていきます。
目次
システム開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国6000社以上からご提案
1.システム改修とは?
●システム改修の意味
システム改修とは、新しい機能を追加したり、デザインを変えたりして、現状のシステムよりも使いやすい仕様にすることです。
そもそも改修という言葉は、本来であれば「悪い部分や壊れている箇所を直すこと」を意味します。道路や建物の工事などに使われるイメージを持つ方も多いでしょうが、必ずしも悪い部分や壊れている箇所を直すことのみを指すだけではなく、より良いものに改善・改良する意味も含まれます。
●システム改修とシステム開発の違い
システム開発は、新しくシステムを作成するという点で、既存のシステムを修正・変更するシステム改修とは異なります。システム改修の大きなメリットは今までのシステムをそのまま活用できることです。1からシステム開発をおこなうわけではなく、あくまでも改修になるので、使い慣れたシステムを引き続き使うことができます。
2.システム改修を行う主なタイミング・目的
システム改修を検討するタイミングは企業によってそれぞれですが、代表的な例としては以下のタイミングや目的が挙げられます。
●法改正などにより時代に合わなくなった
消費税の制度改定や新たな元号の決定などにより、社内のシステムを改修する必要が出てくるケースが考えられます。また、該当する業界に関連する法改正が行われたときも同様に、法令遵守の観点からシステム改修を行うことは必須となるでしょう。法律や制度の改正がわかった段階から早めに取り組むことが重要です。
●不具合がある
システムは長く使い続けることで、「システムの動きが遅い」などの不具合が表面化することがあります。また、サーバーOSやミドルウェアのサポート終了やアップデートによる影響で不具合が起こり、システム改修が必要になることもあります。さらに、システム改修を行うことで、まれに別の不具合が発生してしまうケースもあるため要注意です。
●より使いやすく改善したい
正常に作動はするものの、操作方法がわかりにくく、ミスが発生しやすい場合はシステム改修を検討しても良いでしょう。操作性を改善することで業務効率の向上が見込めます。
●機能を追加したい
業務効率化の観点から、アラートや自動化など新たに機能を追加したいニーズが出てきたときもシステム改修のタイミングと言えます。ただし、新機能の追加は場合によってはシステムの二次開発ともいえる大規模改修になるため、開発会社に相談して費用対効果を検討しましょう。
【関連記事】
▷「業務を自動化させるツールの導入方法は?導入までの流れや失敗してしまう原因などについても解説!」
3.システム改修の一般的な流れ
システム改修の流れについては改修の規模や会社によっても異なるため一概には言えませんが、一例として以下に流れを紹介します。
●1.打ち合わせ
まずはシステム開発会社と発注者で打ち合わせをおこないます。この際に既存システムの機能、構成をしっかり共有しましょう。また、「どのように改修したいか」という要望についても明確に伝える必要があります。その内容を加味して見積もりを出してもらうことになります。
●2.設計
この工程で改修費用やスケジュールを確定させます。既存プログラムの分析やデータ構造解析、問題点の洗い出しなどをおこなって改修の内容設計書を作成するといった流れです。
●3.開発
決定した改修内容に基づいてシステム改修を開始します。新システムのプログラミングを行った後、改修内容による不具合が起こっていないか、単体テストや結合テストなどの動作検証を実施します。
●4.完成・納品
無事に改修が完了したら、本番環境にて動作検証をおこないます。動作検証にて不具合などが発生した場合、その修正対応をおこなって納品です。
●5.保守・運用
システム改修が完了した後においても問題なく運用できるように随時チェックしていくことになります。この工程が入ることによって改修したシステムを継続的に活用することができるのです。
4.システム改修の費用の目安
システム改修にかかる費用は、主に人件費と諸経費に分かれています。人件費は作業を行うエンジニアやプログラマーにかかる費用で、諸経費には改修に必要な機材・ソフトウェアなどの代金が含まれます。
人件費の算出には「人月」という単価が用いられています。これは、システム改修に必要なスタッフの人数に1人当たりの作業期間(月単位)を掛けたものとなっています。
「人月」の相場は、システム開発会社のスタッフの役職や規模(従業員数)により異なります。一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会の報告書によれば、東京のシステム開発会社における人月単価の相場は以下の通りです。なお、地域差もあり、東京など都市部の人月単価のほうが高くなるという傾向もあります。
■<東京のシステム開発会社における人月単価(万円/人・月)の相場>
| PM | リーダー | サブリーダー | メンバー | |
| 従業員数1000人以上 | 158.0 | 141.0 | 121.2 | 98.0 |
| 従業員数500人以上1000人未満 | 125.9 | 110.6 | 96.9 | 83.4 |
| 従業員数500人未満 | 104.6 | 91.7 | 80.1 | 71.0 |
【出典】一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会「IT価格相場運営プロジェクト研究成果報告書 2021年4月」
5.システム改修の費用を抑えるコツ
●自社の対応範囲を増やす
システム改修作業自体を自社で行うことが難しい場合、そのほかの作業をなるべく自社で行うようにし、システム開発会社の工数を削減すると費用の総額を抑えることができます。
例えば、システム改修時のマニュアル修正などはスキルを問わないため、可能であれば自社で修正対応すると良いでしょう。また、テストデータの作成も一般的にはシステム開発会社が用意しますが、自社側でデータやテストパターンを用意しておくのも費用削減につながるでしょう。
●改修箇所を明確化する
どの部分をどのように修正したいのか、どんな機能を追加したいのかなど改修箇所を明確化しておけば費用削減につながります。というのも、依頼内容が明確になるほど、システム開発会社は人月を予測しやすいため、見積もりの精度が高くなるからです。依頼内容に不確定要素が多くなれば、システム開発会社はどうしてもリスクヘッジのために工数を多く見積もるため、結果として改修費用が高額化しやすい傾向にあります。
●改修依頼のやり取りを少なくする
修正箇所が多くても少なくても、システム改修の流れは大きく変わりません。そのため、後から追加で細かい修正を加えるたびに、システム開発会社にはテスト工程作業が増えていくため、結果的に改修費用は高額化しやすくなります。改修の依頼は最初にまとめて行い、その後の修正のやり取りを減らすようにしましょう。
●月額制・定額制を検討する
場合によっては、システム開発会社の月額制・定額制サービスを利用するほうが費用を抑えられることがあります。利用頻度が多くなりそうな場合は検討しても良いでしょう。
月額制・定額制の受託開発サービスについて詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。
▷月額制・定額制の受託開発サービスは利用しやすい?仕組みや事例について解説!
6.システム改修の費用が高くなりやすいケース
●広範囲に修正するケース
1箇所の修正であっても広範囲に影響を与える場合は、結果的に修正箇所が増えるため改修費用の総額は高くなりやすいと言えます。例えば、画面の表示に修正を加える場合は、画面の数に応じて修正が必要になるため、費用が掛かります。ただし、プログラムの内容によっては、画面数が比例しない場合もあります。
●データベースの改修が必要なケース
改修に伴い、参照しているデータベースの改修も必要となるケースがあります。この場合は変換ツールの作成やデータ移行など作業が増えるため、改修費用は高くなります。
●テストに工数がかかるケース
改修内容によっては、テスト項目が増えたり、複雑なパターンのテストが必要になったりすることがあります。システム開発会社の作業工数が増えるため、改修費用は高くなりがちです。
7.システム改修の際に気をつけたいこと
●デグレードテストを行う
システム改修において忘れてはいけないことがデグレードテストです。
デグレードテストとは、プログラムに手を加えたことによって、今まで正常に動いていた部分が動かなくなっていないかを確認するためのテストです。
システム改修によっておこなった処理が正常に反映されているかをテストするのはもちろんですが、同時にこのデグレードテストを必ずおこなわなければなりません。
簡単なデグレードテストの方法として、プログラムの修正前と後で同じ環境を用意し、それぞれで動かすことが挙げられます。
修正前と後で同じ結果が返ってくれば問題なく改修が完了していると考えてよいでしょう。
●場合によっては、新規の作り直しも検討する
求めるシステムの内容によっては、既存システムを改修しながらそのまま利用し続けるよりも、新規で作り直したほうがコストも時間も少なく済む場合があります。
新規で作り直したほうが良いケースとして代表的なものは、独自のフレームワークを利用したシステムの場合です。もともと担当してもらっていたシステム開発会社に何らかの理由で改修を依頼できなくなった場合、他社に依頼することとなり、既存システムの解析が必要になります。独自のフレームワークの場合は解析に時間がかかるため、かえってコストがかかり、新規で作り直したほうが良いケースがあるのです。
●改修に伴い、マニュアルやフローを整備する
改修に伴って、変更になったオペレーションについてマニュアルを修正し、社内フローもスムーズに移行できるよう調整しておきましょう。マニュアルはシステム開発会社にも依頼できますが、なるべく自社で行うようにしておけばコスト削減にもつながり、今後自社の社内体制変更が起こるたび、その都度対応できるようになります。
システム開発の最適な発注先をスムーズに見つける方法
システム開発会社選びでお困りではありませんか?
日本最大級のシステム開発会社ポータルサイト「発注ナビ」は、実績豊富なエキスパートが貴社に寄り添った最適な開発会社選びを徹底的にサポートいたします。
ご紹介実績:25,000件(2025年05月現在)
外注先探しはビジネスの今後を左右する重要な任務です。しかし、
「なにを基準に探せば良いのか分からない…。」
「自社にあった外注先ってどこだろう…?」
「費用感が不安…。」
などなど、疑問や悩みが尽きない事が多いです。
発注ナビは、貴社の悩みに寄り添い、最適な外注探し選びのベストパートナーです。
本記事に掲載するシステム会社以外にも、最適な開発会社がご紹介可能です!
ご相談からご紹介までは完全無料。
まずはお気軽に、ご相談ください。 →詳しくはこちら
システム開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国6000社以上からご提案
■システム改修に関連した記事