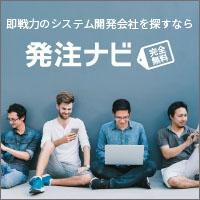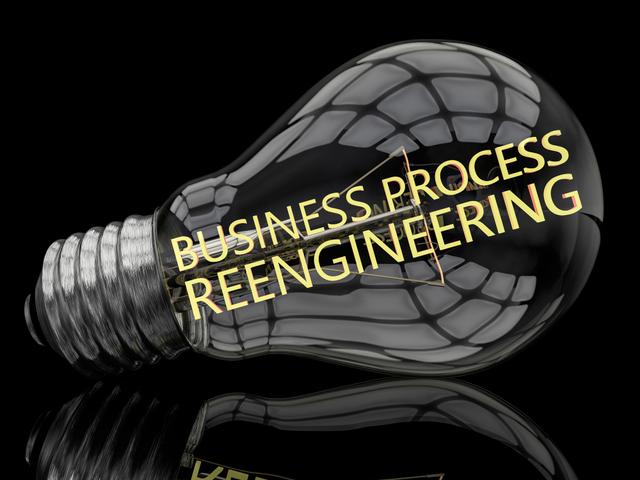
組織の業務フローを抜本的に見直し、業務の効率化や生産性向上を推進するのに役立つ手法が「BPR」です。BPRの基本的な情報をはじめ、BPRを実現するメリットや推進時の注意点、具体的な計画の進め方を紹介します。
目次
システム開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国5000社以上からご提案
BPR(Business Process Re-engineering)とは業務改革のこと
BPRは、「Business Process Re-engineering(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)」の頭文字を取った言葉。現在の業務フローや組織内の構造、使用している情報システムを見直して再構築し、業務改革することを指します。米国の大学教授マイケル・ハマー博士と経営コンサルタントのジェイムス・チャンピー氏による共著「リエンジニアリング革命」で広まった考え方であり、90年代から日本企業でも導入されてきました。
●BPRと類似する用語との違いや関係性
業務改善やDX、ERPなど、BPRと類似する用語は少なくありません。それぞれの特徴とBPRとの違いや関係性を、以下で解説します。
業務改善とは何が違う?
業務プロセスや組織構造を全体的に見直すBPRに対し、「業務改善」は一部の業務フローや内容を見直すことを指します。また、BPRと業務改善では見直しのスケールにも違いがあります。BPRは業務プロセスに大きな改革を起こすのに対し、業務改善は業務単位で少しずつ、部分的に改善を進めます。BPRと業務改善を比較すると、BPRのほうがより大きな影響を与えるといえます。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは何が違う?
DX(デジタル・トランスフォーメーション)とBPRの違いは、ビジネスモデルを変革するか否かにあります。DXは、IT・デジタルツールを用いて「ビジネスモデル」を変革することが目的です。対するBPRの目的は、「組織内のプロセス」を改革することにあります。とはいえ、「ゆくゆくは業務の改革につなげる」という大きな目的は共通しているといえます。
ERPとBPRとは何が違う?
ERPとは、「経営資源計画」のことです。組織内の資源を適切に管理・活用するための計画だと捉えましょう。くわえて、経営資源計画を進めるための各種システムも「ERP」と呼ばれます。ERPを導入することで、業務や組織全体の情報を正確に掴めるようになり、業務改革がより効率的に進みます。BPRを推進するためにも欠かせない要素です。
BPRにはどんなメリットがある?
BPRを実現することで、組織はどのような恩恵を受けられるのでしょうか。業務の効率化や経営判断のスピードアップなど、BPR実現によって得られるメリットを3つご紹介します。
●1.業務効率化につながる
BPRでは、全業務のフローやプロセスを可視化します。これにより、業務ごとにある効率化を阻む課題点が見つけやすくなります。例えば、「複数の部門で業務が重複し、ロスが発生している」「作業マニュアルが整備されておらず部門ごとの生産性にムラがある」といった課題点が明らかになります。課題点が明確になれば改善策を立てやすくなり、業務効率化につながります。
●2.スピーディーな経営判断につながる
BPRに取り組むことで、迅速な経営判断や意思決定を妨げている要因も特定されます。くわえて、意思決定のフローが最適化される効果も期待できます。これにより、経営判断のスピードアップにつながります。経営判断がスピーディーになることで、機会損失のリスクを防ぎ組織全体の競争力が向上することも見込めます。
●3.従業員のやりがいや顧客満足度向上にもつながる
BPRによって業務が効率化されれば、従業員の業務負担が軽減されます。形骸化していたルールや非効率なフローが撤廃されることで、従業員が働きやすくなります。くわえて、より重要度の高いコア業務に注力しやすくなり、商材やサービスの品質向上も期待できます。商材・サービスの品質が高まれば顧客満足度が向上し、組織全体の価値が高まります。
BPRのデメリット・注意点
BPRを実践するにあたり、押さえておきたいデメリットは以下の2点です。メリットだけでなくデメリットもしっかりと把握しておき、BPR計画を進めましょう。
●実行には大きな労力やコストがかかる
BPRの対象範囲は社内全体となります。社内全体の業務改革を目的としているため影響が大きく、成功させるためには大きな労力が必要です。BPRを完遂できずに改革を断念すると、大きな混乱だけが残ることも考えられます。計画内容によっては新しい情報システムの導入や一部業務のアウトソーシングを行うこともあるため、費用面の負担も大きくなります。
●社員の負担が大きくなる可能性がある
BPRは社内全体を巻き込む改革計画であるため、社員一人ひとりの負担が大きくなる可能性があります。結果的に現場の社員の業務が圧迫されて思うように理解が得られず、経営層と社員の間に溝が生まれることもあります。社員の協力を得るためには、事前の周知や情報共有を徹底することが大切です。「何のためにBPRを行うのか」「BPRを実践することでどのような恩恵を受けられるのか」という点を、社内全体に根気強く周知しましょう。また、経営層のみで話を進めるのではなく、現場のキーパーソンを企画段階から巻き込むことも大切です。
具体的なBPRの手法とは?
一言でBPRといっても、その手法は多様です。業務の仕分けを行ったうえで適切な手法を選び、組み合わせて実践することが大切です。以下では、BPRの手法を4つピックアップしました。
●ERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)システムの導入
ERPシステムとは、予算・財務会計や在庫、人材など組織内の幅広い情報を一元的に管理できるシステムです。ERPシステムを導入することにより、部署や部門間でバラバラに管理していたデータを集約でき、BPRの推進に役立ちます。くわえて、経営資源に関する課題も見つけやすくなり、経営資源計画の適正化にもつながります。
●シックスシグマの実践
シックスシグマとは、1980年代に開発された、統計学に基づいた品質管理のフレームワークのことです。以下の内容をもとに業務プロセスを改善していきます。
-
Define(定義)
-
Measure(測定)
-
Analyze(分析)
-
Improve(改善)
-
Control(管理)
自社が抱える課題を定義したうえで、各業務プロセスで発生する工数やサービス・商品の品質のばらつき(エラー例)を測定分析し、改善のためのアクションを実践するのがシックスシグマです。
●BPO(Business Process Outsourcing)の検討・導入
BPOとは、「Business Process Outsourcing:ビジネスプロセスアウトソーシング」の略称です。業務プロセスを、一括してアウトソーシングすることを指します。通常のアウトソーシングとは異なり、業務のいち部分ではなく企業の業務プロセスごと、一括してアウトソーシングするのがBPOの特徴です。これによって社員の業務負担が軽減されるだけでなく、コア業務に集中しやすい環境もつくれます。BPOの対象となる業務として挙げられるのは、受付や経理、ヘルプデスクといったバックオフィス業務が中心です。
●SCM(Supply Chain Management)の検討・導入
SCMとは「Supply Chain Management:サプライチェーンマネジメント」の略称です。サプライチェーンとは、サービスや商品が生産されてから顧客へ供給されるまでの流れのこと。SCMでは、それぞれの情報を部門間・企業間で共有し、サプライチェーンの最適化・効率化を目指します。
SCMを実践し、在庫の最適化や販売チャネルの見直しを行えばさらなる業務効率化につながります。くわえて、サプライチェーンが最適化されれば消費者の満足度向上も期待できます。
企業でBPRを実施するステップ
BPRを成功させるためのステップを、以下で解説します。業務フローの見直しに始まり、目的の明確化や施策の実行、PDCAを回すに至るまでの流れをチェックしてみてください。
●業務フローを見直す
業務を棚卸したうえで、フローを見直すフェーズです。社内全体の業務フローを明らかにすることで不要な工程が見つかったり、形骸化している作業が明らかになったりします。業務効率化のボトルネックとなっている箇所が発見できるため、現在抱えている経営課題の顕在化につながります。業務フローの見直しを通して、業務改革を阻んでいる課題点の全体像をハッキリとさせておきましょう。
●BPRの目的を明確にする
問題の全体像が明らかになったら、「何の目的でBPRを実施するのか」「BPRの対象となる部署や業務はどこか」「期待する効果」といった目的を明確にしましょう。対象となる部署や業務を絞り込み、目的(ゴール)を決定することで、計画の迷走を防げます。対象の絞り込みやゴール設定が曖昧だと不要な作業が発生してしまい、思わぬコストがかかることも考えられます。
●戦略や方針を決定する
BPRの対象が明確になったら、具体的な改革方法を立案します。例えば、「この業務は本当に必要か・簡略化できないか」「BPOの考え方に基づいてアウトソーシングできるか」「システムの導入で自動化できないか」といった観点から戦略を立てるのがおすすめです。抜本的な改革を行うという性質上、BPRは企業のトップや役員などが中心となって計画を進行します。ただし、BPRを成功させるためには全社員の協力が不可欠です。事前の周知を徹底することはもちろん、戦略や計画の策定には現場の社員を交えて意見を交換しあい、方向性を定めていくことが大切です。
●決定した施策の実行
戦略や方針が決定したら、計画を実施するフローへ移行します。BPRの旗振り役は企業のトップや役員が担いますが、情報共有が後手に回ると現場に混乱が生じやすくなります。事前共有はもちろんですが、計画実行中にもリアルタイムで情報共有を行い、混乱を最小限に抑えましょう。各部門にBPR推進のプロジェクトリーダーを置き、部門ごとの進捗状況を把握・管理するとスムーズに進みます。
●PDCAを回す
計画を実施できた後でも、PDCAを回してBPRの効果を検証しましょう。効果が不十分の場合は、その都度計画を修正する必要があります。また、期待どおりの結果が出たとしても、検証を続けてより高い効果を追求するのも良い方法です。なお、成功と失敗のどちらにしても、再び業務改革を実施する時に備えて、計画や実施の内容を細かく記録しておくことをおすすめします。
BPR推進で重要な役割を担う基幹システム
BPRを推進する手法の1つとして、「各種基幹システムを導入して業務を効率化する」という方法があります。基幹システムとは、その名のとおり企業が業務を遂行するうえで必須となる機能を備えたシステムのことです。具体的には、「販売管理システム」「在庫管理システム」「受注管理システム」「会計システム」などが基幹システムにあたります。
●基幹システムの例1:販売管理システム
商品の販売を管理するためのシステムです。販売管理業務の負担軽減につながります。
商品をユーザーへ届けるまでのお金と商品の流れを一元管理できるシステムだと考えると良いです。売上や見積もりを管理できるほか、在庫管理機能や購買管理機能が搭載されているシステムが多くみられます。また、受注管理システムや会計システムなどの外部システムと連携可能なものも少なくありません。販売業務に関する情報を一元管理できるためミスの防止にもつながり、結果的にBPRの推進にも役立ちます。
●基幹システムの例2:在庫管理システム
在庫管理業務全般の機能が搭載されたシステムです。在庫の検索や、入出荷情報をリアルタイムで確認しながら管理できるため、在庫の適正管理には欠かせません。在庫管理システムを活用することで、在庫管理・棚卸業務の負担を軽減できます。くわえて、手動・目視による入力ミスや計算ミスも防げるため、正確なデータを割り出せます。
●基幹システムの例3:受注管理システム
商品を受注してから生産・発注するまでのプロセスを管理するためのシステムです。これまでの受注業務では、電話やメール、FAXで受けた注文内容を伝票へ出力したり、Excelへ転記したりといった作業が必要でした。受注管理システムを導入することで注文をWebから一括で受け取れるようになり、転記の手間を省けます。手入力する必要もないため、記入や転記ミスの防止にもつながります。
●基幹システムの例4:会計システム
会計業務全般を管理するシステムのことです。会計業務は、日々の支払い管理や帳票の作成、仕訳入力など煩雑な作業が少なくありません。これらの作業をすべて手動で行うとなると、業務負担が増加する原因となります。
例えば、導入することで仕訳データを入力するだけで試算表や帳票などの書類を自動作成でき、各種作成作業を簡略化できるようになります。転記漏れによるミスも防止でき、会計業務全般の精度が向上するのもポイントです。
BPR推進に役立つシステム開発なら発注ナビへ
フレームワークの導入や各種基幹システムの導入など、BPRの推進方法は様々です。BPRを成功させるためには、自社の業務フローや課題点、組織体制に合わせた手法を見極める必要があります。
BPR推進の一環として各種システムの導入を検討されている方は、発注ナビへお任せください。システムの開発や導入支援を得意とする企業を、独自のネットワークより厳選して紹介します。
ご紹介実績:18,000件(2023年12月現在)
外注先探しはビジネスの今後を左右する重要な任務です。しかし、
「なにを基準に探せば良いのか分からない…。」
「自社にあった外注先ってどこだろう…?」
「費用感が不安…。」
などなど、疑問や悩みが尽きない事が多いです。
発注ナビは、貴社の悩みに寄り添い、最適な外注探し選びのベストパートナーです。本記事に掲載するシステム会社以外にも、最適な開発会社がご紹介可能です!
ご相談からご紹介までは完全無料。まずはお気軽に、ご相談ください。→詳しくはこちら
システム開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国5000社以上からご提案
■BPRに関連した記事